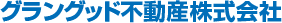不動産を売却するときには、不動産の名義によって必要な手続きや合意内容などが異なります。共有名義のままでは思い通りに売却を進められないケースも多いため、まずは「不動産の名義の仕組み」や「持分の考え方」について正しく理解しておくことが重要です。
共有名義と単独名義の違い
不動産の所有形態には、「単独名義」と「共有名義」の2種類があります。単独名義とは、一人の所有者が不動産の権利を100%持っている状態で、売却や賃貸などの手続きを、全て自分の判断で進められます。
一方で、共有名義とは、複数人で同じ不動産を所有している状態のことです。例えば親からの相続や夫婦での購入、兄弟姉妹との共有などが該当します。共有名義では、不動産の売却などを進める際に、原則として共有者全員の合意が必要です。
「持分」とは?自分の権利の範囲を正しく理解する
共有名義による不動産の所有は、「持分(もちぶん)」という概念に基づいています。持分とは、不動産の中で自分がどの程度の権利を有しているかを数値で示したものです。例えば、兄弟2人で50%ずつの持分を持っている場合は、同じ不動産についてそれぞれが半分の権利を有していることになります。
持分は登記簿に記載されており、この割合に応じて売却益の配分や意思決定への関与割合が決まります。ただし、持分があるからといって「その分だけの土地や部屋を自由に使える」というわけではありません。
持分は不動産の物理的な所有部分を示すものではなく、処分などする際には、他の共有者との調整が必要です。持分がある不動産の売却を検討する際は、自分の持分がどれくらいか、そしてどこまでの判断が単独で可能なのかを把握しておきましょう。
なぜトラブルが多い?共有名義の不動産が抱える問題点

共有名義の不動産を売却する際などには権利や意思決定の調整が必要ですが、話が思うように進まないことも少なくありません。特に売却や活用といった場面では、共有者間で意見の対立や手続きの停滞が起こりやすく、結果として「売れない不動産」になってしまうこともあります。
よくある4つの対立パターン
共有名義の不動産を巡っては、以下のような対立がよく起こります。
一方は売りたいが、他方は住み続けたい(居住 vs. 売却)
典型的なケースは、兄弟で相続した実家に一方が住み続け、もう一方は売却を望むというものです。この場合は特に、感情的な対立に発展しやすいものです。
費用の負担を巡る揉め事
固定資産税や修繕費などの費用を誰がどの割合で負担するのか、話し合いが不十分だと不満や不信感が生まれます。特に負担が偏っていると感じる共有者は、不動産を売りたがることが多いものです。
連絡が取れない共有者がいる
共有者の一部が遠方に住んでいたり、高齢や認知症により判断能力が低下していたりといった場合は、協議そのものが成立しません。これも売却の手続きが止まる理由としてありがちです。
相続時に持分を巡って対立していた
遺産分割時の感情的なわだかまりが解けず、売却時にも不信感を引きずるケースがあります。「あのときは譲ったから、今回は…」といった持分調整の不満が再燃することも多いものです。
売却に必要な「合意」の範囲とは?
共有名義の不動産を売却する際には、全ての共有者が同意しないと売れないのが原則です。不動産の売却は「共有物の処分」に該当するため、法律上、全員一致の合意が必要となります。たとえ自分が過半数の持分を持っていても、単独で売却手続きを進めることはできません。
一方で、軽微な利用(修繕や賃貸など)に関しては、持分の過半数での決定が認められる場合もあります。しかし、売却は「重要な処分行為」と位置付けられるため、全員の合意が必須です。
このため、一人でも反対すれば売却は実現できず、交渉が長期化したり、最悪の場合は訴訟に発展したりすることもあります。売却を考える際には、まず共有者との関係性を整理し、合意形成に向けた準備を整えることが求められます。
具体的には、全共有者の署名・押印、実印、印鑑証明書の提出、登記識別情報の提供などが必要です。これらは売買契約書の作成や所有権移転登記の際に不可欠な要素であり、一人でも応じなければ手続きは進められません。
特に、相続や離婚後で連絡が取りづらい共有者がいる場合、「売却の同意」と「書類手続きへの協力」がセットで必要になる点に注意が必要です。
言い換えれば、話し合いでの了承だけでなく、実務上の協力(書類提出)が揃って初めて売却が成立するということになります。要件をあらかじめ整理して、共有者と早めに話し合いしておくことが、スムーズな売却への第一歩です。
共有名義の不動産を売却する5つの方法とその進め方

共有名義の不動産を売ろうとすると、必ずしも全員が納得するとは限りません。そんなときは、状況に応じた解決策を探る必要があります。共有者全員での売却から、持分のみの売却、訴訟による解決まで、5つの主要な手段を紹介します。
方法①:共有者全員で売却する(最もおすすめ)
共有名義の不動産を売却するうえで、最もスムーズかつトラブルが少ないのが、共有者全員の合意を得て売却する方法です。全員の同意があることで、不動産としての価値を保ったまま売却が可能になります。
この方法では、不動産仲介会社を通して買主を探し、買主と売買契約を締結します。売買契約書には共有者全員が署名・押印し、売却代金は持分に応じて分配するのが一般的です。なお、名義や登記の変更手続きは、司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
方法②:自分の持分だけを売却する(第三者への売却)
共有者の合意が得られない場合でも、自分の持分だけを第三者に売却することは法的に可能です。ただし、この方法には大きなデメリットが二つあります。一つ目のデメリットは買手が見つかりにくいことです。
買手は不動産の共有持分を購入しても、単独で不動産を使ったり処分したりできません。買手から見ると、共有不動産の持分だけを購入するメリットは小さいといえます。このため、共有持分だけを購入する買手は限られるのが実態です。
二つ目のデメリットは「売れたとしても問題が終わるとは限らない」ことです。買主が投資目的であれば、他の共有者に対して共有物分割請求訴訟を起こし、物件全体の売却を求めることもあり得ます。
つまり、自分の持分を売却したあとに、他の共有者が知らない第三者と法的トラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
また、こうしたリスクがあるために、持分だけの売却価格は通常の市場価格より大幅に低くなる傾向があります。買手が限定されるうえに、現金化はできても「希望額での売却実現」は期待しにくいのが実態です。
なお、他の共有者にとっても、見知らぬ第三者が突然不動産の共有者になることは心理的な負担となり、今後の関係が悪化する恐れもあるでしょう。
したがって、単独での持分売却はあくまで最終手段と考え、まずは共有者間での協議・交渉を優先するのが基本です。それでも解決が難しい場合に限り、買取業者の利用などを選択肢として検討するのが現実的といえます。
方法③:他の共有者に持分を売却する(家族内取引)
信頼できる共有者がいるならば、自分の持分を共有者に買い取ってもらう「家族内取引」も現実的な選択肢です。例えば、兄弟間で共有している実家の持分を、実際に住んでいる兄が買い取るといったケースが該当します。
この方法では、第三者が関与しないためトラブルも起きにくく、親族内で話し合いがまとまればスムーズに手続きが進むでしょう。
売買価格は市場価格を参考に設定し、名義変更の登記手続きは司法書士に依頼すると安心です。持分譲渡といえども正式な売買契約が必要で、譲渡益に課税されることもあるため、事前に税務上の確認もしておくと良いでしょう。
方法④:土地を分筆して単独名義にして売却する
土地の共有物件であれば、物理的に分割して分筆登記を行い、それぞれが単独名義とする方法もあります。分筆によって自分の単独所有部分ができれば、その部分だけを自由に売却可能です。
ただし、土地を分筆するためには測量や境界確定が必要で、時間と費用がかかります。また、分筆できるかどうかは、土地の形状や法的制約(都市計画法、建築基準法など)にも左右されるため要注意です。
分筆後にできあがる区画の資産価値が下がる場合もあるため、不動産会社や測量士と連携しながら慎重に進める必要があります。
方法⑤:共有物分割請求訴訟で法的に解決する
共有者間の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こすという最終手段があります。訴訟を起こすことで、不動産を分ける(現物分割)か、売却して代金を分ける(換価分割)ように命じてもらうことが可能です。
裁判所は原則として「現物分割」を優先しますが、不可能な場合は競売や任意売却による換価分割となります。ただし、この方法は時間がかかるうえに、共有者間の人間関係がさらに悪化する恐れもあります。
また、競売では市場価格よりも安く売却されてしまうことが大半です。可能な限り、訴訟になる前に第三者を交えた調整を行うのが望ましいといえます。
売却時に発生する費用・税金・分配のルール

共有名義の不動産を売却する際には、「費用」「税金」「売却代金の分配」に関するトラブルが発生しやすいものです。トラブルなく手続きを進めるためには、あらかじめそれぞれのポイントを理解し、共有者間で認識を揃えておくことが必要です。
売却時にかかる代表的な費用一覧
不動産を売却する際には、次のような費用が発生します。共有名義であっても、基本的には単独名義のケースと大きな違いはありません。
仲介手数料(不動産会社へ)
仲介手数料は売買価格に応じて上限が決まっており、売却代金の3%+6万円(税抜)が一般的です。
登記関連費用(司法書士へ)
所有権移転登記や抵当権抹消登記などの手続きに必要な費用です。
測量費・境界確定費
土地を分筆・整備する場合には必要になります。
契約書に貼付する印紙代
売買価格に応じて定額で課税されます。
これらの費用は、共有者がそれぞれの持分割合に応じて負担するのが一般的ですが、話し合いによって調整することも可能です。
税金(譲渡所得税・贈与税・確定申告)の注意点
不動産売却によって利益(譲渡益)が出た場合は、譲渡所得税が発生します。譲渡所得税は、売却代金から取得費(物件購入時の物件価格)や譲渡費用(売却にあたってかかる諸経費)などを差し引いた残額に対して課税される税金です。
売却する不動産が共有名義であれば、それぞれの持分に応じて譲渡所得を計算し、各共有者が個別に確定申告を行う必要があります。
注意すべきは、「売却益を共有者の一人にまとめて渡す」などの不自然な資金移動をすると、贈与税の課税対象となってしまう可能性があることです。たとえ家族間であっても、贈与とみなされる行為には慎重になる必要があります。
また、譲渡損が出た場合や居住用財産の特例(3,000万円控除)など、節税対策が有効になるケースもあるため、早い段階で税理士に相談しておくと安心です。
売却代金を分ける際に揉めないための注意点
売却後の代金の分配で揉めるのを防ぐには、あらかじめ共有者間で取り決めを明確にしておくことが重要です。原則として、分配は「持分割合に応じて」行いますが、過去に片方が固定資産税を多く支払っていたり、リフォーム費用を負担していたりした場合など、実情に応じて調整が必要になる場合もあります。
トラブルを防ぐためには、以下の対応が有効です。
- ・分配方法を文書で記録に残す
- ・話し合いで合意した内容を売買契約書や覚書に反映させる
- ・中立的な第三者(司法書士・税理士)を入れて話し合いをする
特に親族間での話し合いにおいては、「言った・言わない」の水かけ論に発展しやすいため、書面で証拠を残すことがトラブル回避の鍵となります。
なお、売却時に発生する仲介手数料や登記費用、税金の支払いをどのように分担するかについても、あらかじめ全員で協議しておくと安心です。ただ、通常は、売却代金から諸費用を差し引いた残額を持分割合に応じて配分するのが一般的です。
よくある悩みと福岡での相談ニーズに応えるには?

共有名義の不動産を売却する過程では、「相手と連絡が取れない」「共有者の判断能力に不安がある」など、地域性に関わらず共通する悩みが多く見られます。
一方で、地元に根ざした対応力や専門知識を持つ不動産会社に相談することで、具体的な打開策が見えてくるケースも少なくありません。
「共有者が反対している」「連絡が取れない」場合の対処法
売却にあたって共有者の一人が反対している場合には、まずは合意形成を試みることが第一です。共有者の理解を得るためには、売却の必要性や資産状況を丁寧に説明し、書面などで提案内容を共有するとよいでしょう。
それでも進展がない場合には、家庭裁判所での「共有物分割調停」や、最終的には共有物分割請求訴訟を通じて法的に解決を図ることになります。
また、連絡が取れない共有者がいる場合は、不在者財産管理人の選任申し立てを行うことで、売却手続きを進められる可能性もあります。
そのほか、共有者の所在が不明な場合には、「公示送達」と呼ばれる方法を用いて訴訟手続きを進めることも可能です。これは、家庭裁判所が公告をもって連絡不能者に通知したものとみなす制度で、法的な手続きを強行できる手段の一つです。
さらに、売却がまったく進まずに放置されることで固定資産税の負担だけが続く場合などは、競売という形での解決も視野に入れると良いでしょう。
例えば福岡では、所有者の高齢化や相続をきっかけとして共有名義化した物件が多く、実際に「連絡が取れない」「気まずくて話せない」という相談が寄せられることも少なくありません。こうした手続きを検討する際には、専門知識が不可欠となるため、早い段階で弁護士や司法書士に相談し、選択肢を整理することが重要です。
「どうせ無理だ」と諦める前に、まずは無料相談などを通じて、自分のケースで可能な道を探ることが賢明といえます。
高齢の共有者や認知症のリスクにどう備える?
高齢の共有者がいる場合には、判断能力が低下する前に早めの手続きを進めることが重要です。認知症を発症してしまうと、本人の意思確認ができなくなり、売却が難しくなってしまいます。
すでに判断能力に疑義がある場合は、成年後見制度の利用が必要になります。家庭裁判所に申し立てて後見人を立てることで、売却手続きを進めることが可能です。しかし、時間と手間がかかるため、とにかく早めに相談することが重要です。
特に福岡県内では、親が高齢化して実家を売却したいという子世代からの相談が増加しています。こうしたケースでは、相続や後見に強い司法書士と連携して、法的なバックアップを受けながら丁寧に段取りを組むことがトラブル回避の鍵となります。
司法書士や不動産会社に頼めること・頼むべきこと
共有名義の不動産を売却する際には、司法書士と不動産会社の双方に必要なことを依頼するのが成功のポイントです。司法書士に依頼できることは、以下の通りです。
- ・所有権移転登記や名義変更の手続き
- ・持分売買契約書の作成
- ・成年後見や相続登記の相談・申請手続き
一方で、不動産会社には以下のことを依頼できます。
- ・買主の募集・販売活動
- ・売却価格の査定と提案
- ・共有者間の調整サポート(必要に応じて)
例えば、福岡のように地域に根ざした不動産市場では、地元事情に通じた不動産会社が相場感・買手ネットワーク・調整力を備えていることも多く、共有名義の不動産を売却する際にも頼れる存在になります。
専門家のアドバイスを適切に活用しながら、感情的な対立を避け、スムーズな売却を目指すことが重要です。
福岡県内で「共有名義の不動産売却」を相談するなら
共有名義の不動産売却には、専門知識と調整力、そして地域事情に対する深い理解が欠かせません。福岡県内で安心して相談したいなら、地域に密着した実績のある不動産会社を選ぶことが、成功への近道となります。
地元密着型の不動産会社に相談すべき理由
共有名義の不動産を売却する場合には、単なる仲介だけでなく、共有者間の意見調整や地元の買手とのつながり、法的な配慮などが求められます。こうした複雑な案件に対して柔軟に対応できるのが、地元密着型の不動産会社です。
福岡県内の不動産市場で売却を成功させるためには、その地域特有の相場や売れやすいタイミング、買主の傾向といった“土地勘”が必要です。全国展開の大手では拾いきれない地場の情報をもとに最適な販売戦略を提案できる点は、地元密着型の不動産会社が持つ大きな強みです。
また、地元密着型の不動産会社は、地元の司法書士・税理士・測量士などの専門家ともネットワークを持っていることが少なくありません。ワンストップで相談できる体制が整っているのも特徴の一つです。
不安や対立が起こりやすい共有名義の売却こそ、信頼できる地元企業に頼るべきといえるでしょう。
福岡で共有名義の不動産を売るならグラングッド不動産へ
共有名義の不動産を売却するためには、法的な手続きや親族間の調整など、通常の不動産取引とは違った複雑さに対応する必要があります。そんなとき、信頼できる相談先があると大きな安心につながるでしょう。
福岡県で不動産の売却や相続、住み替えの相談を検討されている方には、地元密着型のグラングッド不動産がおすすめです。
グラングッド不動産では、共有不動産の売却についても、共有者間の利害調整や法的な論点も丁寧にサポートしながら、売却までのプロセスを一貫してサポート。ご希望があれば提携する司法書士や税理士とも連携し、複雑な案件でもスムーズに進行できる体制が整っています。
また、地域密着の不動産会社ならではの相場知識とスピーディな販売力で、「売れにくい」とされる共有名義の不動産でも納得の売却実績を重ねています。
売却後の税金・資金計画や、万が一のトラブルへの備えも、丁寧にサポート。将来の住まい探しや資産活用の場面でも、「売ったら終わり」ではなく一生涯の相談パートナーとして対応します。
福岡エリアで「誰に相談したらいいかわからない」とお悩みの方は、まずは一度グラングッド不動産にご相談ください。お客様の状況や背景に応じて最適な選択肢を見つけるお手伝いをさせていただきます。
まとめ
共有名義の不動産を売却するにあたっては、売却の意思決定や手続きにおいて複数の関係者との調整が不可欠であり、感情的な対立や法的な問題が生じやすい特徴があります。
しかし、正しい知識と適切な方法を押さえ、専門家の力を借りることで、スムーズな売却は十分に実現可能です。福岡県内でも相続や共有名義化による売却ニーズは年々高まっており、地域に根ざした信頼できる不動産会社に相談することが、安心・納得の取引につながります。