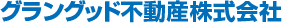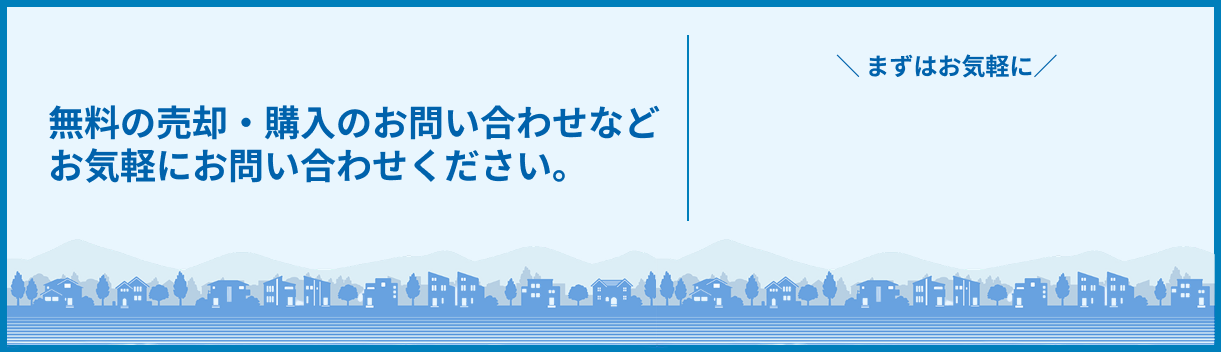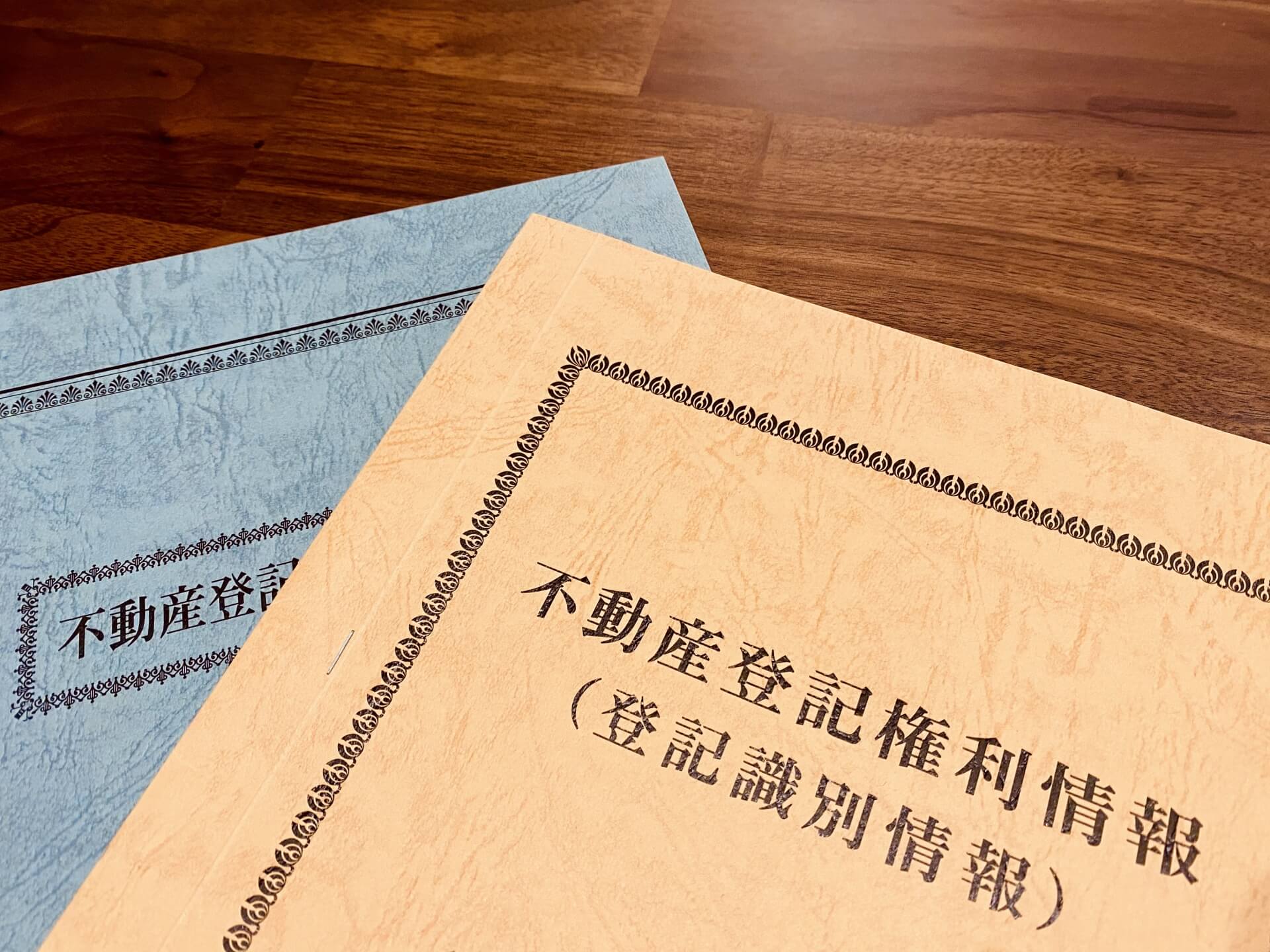「不動産売却の相談って何のため?」から始めよう
不動産の売却を考え始めたとき、多くの人が感じるのは「誰に相談すればいいのかわからない」という不安です。住宅ローンや税金、登記の手続き、さらには親族との関係など、売却にはさまざまな要素が絡みます。
しかし、悩みをひとりで抱え込んでしまうと、時間だけがどんどん過ぎていってしまう可能性もあります。まずは「相談すること」自体の意味を正しく理解し、なぜ早い段階での相談が重要なのかを確認しておきましょう。
誰もが不安になる“最初の壁”とは?
不動産を売却しようと思ったとき、最初に多くの人が感じるのは「誰に相談すればいいのかわからない」「まず何をすればいいのかわからない」という漠然とした不安です。
家や土地を売る機会は人生の中でそう何度もありません。そのため、用意する書類、手続きの流れ、税金の扱い、適正な価格の見極め方など、わからないことが多すぎて手が止まってしまう人も多いのではないでしょうか。
また、「相談」と一口に言っても、不動産会社、税理士、司法書士、弁護士など、専門家の種類が多く、誰にどんな内容を聞けばいいのか迷ってしまいます。
「とりあえずネットで調べたけど、書いてあることが自分のケースに当てはまるのかわからない」という人もいるでしょう。つまり、最初の壁とは「自分に必要な情報を整理できないこと」とも言えるでしょう。
相談から始めることで“損を防ぐ”
不動産の売却においては「売却を決めてから相談する」のではなく、「売却するか迷っている段階で相談する」ことが、損を防ぐためのポイントです。実際、不動産の売却においては、タイミングや契約内容、税金対策の有無などによって、最終的な手取り額が大きく変わることがあります。
例えば、事前に税理士へ相談していれば節税に使える特例があったのに、知らずに確定申告まで進んで損するケースも少なくありません。
あらかじめ専門家に相談しておけば、自分の状況に合わせた進め方を把握できます。インターネットで調べるだけではわからない「自分のケース」に合わせた知識などを得られるのも、相談する大きなメリットです。
まずは押さえたい!不動産売却の全体像

「専門家に相談したいけれど、そもそも不動産の売却ってどんな流れで進むのか?」という疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。売却の基本的な流れを理解しておくことで、各段階でどんな相談をするべきかが見えてきます。
売却のステップを5段階でざっくり解説
不動産の売却は大きく5つのステップに分けて進みます。
ステップ①:売却の意思決定と情報収集
本当に売却するのか、いつ売るのか、売却価格の相場はどれくらいかなど、基本的な情報を集めて方針を決める準備段階です。
ステップ②:不動産会社へ査定依頼・媒介契約の締結
信頼できる不動産会社を選び、物件の査定を受けて媒介契約を結びます。
ステップ③:売却活動(広告・内覧対応など)
チラシや不動産のポータルサイトなどで買い主を募り、買い主の候補者が現れたら現地の内覧や価格交渉などに対応します。
ステップ④:売買契約の締結と手付金の授受
売却価格などの条件が合えば売買契約を結び、引き渡しに向けた手続きに入ります。
ステップ⑤:引き渡し・登記手続き・確定申告などの完了処理
売却代金の決済、鍵の引き渡し、登記手続き、確定申告など、法的・税務的な手続きを進めます。
各ステップで相談できるタイミングは?
つづいて、前項で解説したステップごとにおすすめの相談先を整理します。
ステップ①(情報収集)
まずは不動産会社に相談して、売却の可否や相場感をつかみましょう。この段階では、まだ不動産を売ると決めていなくても問題ありません。
ステップ②(査定・契約)
査定内容や媒介契約について不明点があれば、不動産会社の担当者へ細かく確認しましょう。どうしても不安な場合は、不当な契約内容にならないよう、弁護士などに契約内容を確認してもらうと安心です。
ステップ③(売却活動)
買い主との交渉や内覧対応で困ったら、担当者に任せきりにせず、担当者と相談しながら進めるのが理想です。
ステップ④(契約締結)
契約書の内容や手付金の扱いなど、法的なトラブルが発生しやすいタイミングです。疑問点があれば弁護士や司法書士などに確認しましょう。
ステップ⑤(引き渡し・税務処理)
登記や確定申告の必要書類については、司法書士や税理士に相談して手続きを進めましょう。特例の適用漏れがないよう、早めに確認するのがポイントです。
あなたの悩みに合った“相談先の地図”を持とう

不動産の売却には、さまざまな手続きや判断が必要になります。その中で、「何を」「誰に」相談するかを正しく選ぶことは、売却をスムーズに進めるうえで非常に重要です。相談先を間違えたまま進めてしまうと、トラブルや損失の原因にもなりかねません。
とはいえ、不動産会社・税理士・司法書士・弁護士など、関わる専門家が多く、「誰に何を相談すればいいの?」と迷う方も多いでしょう。不動産売却に関わる主な専門家の役割を整理していきます。
不動産会社:売却の出発点になるパートナー
売却の可否や相場の確認、販売戦略の提案、買い主との調整など、売却活動のほぼ全てをサポートしてくれる「総合窓口」とも言えるのが不動産会社です。
相談時にはまだ売ると決めていなくても問題ありません。また、査定も無料でしてもらえます。不動産会社を選ぶ段階では、担当者との相性も含めて慎重に比較検討すると良いでしょう。
税理士:確定申告・譲渡所得・節税のプロ
不動産売却によって利益が出た場合、その金額に応じた「譲渡所得税」を課税されるため確定申告が必要になります。ここで頼れるのが税金のプロである税理士です。
税理士に相談することで、売却によって得られた利益の計算方法や、利用できる控除・特例の有無を確認できます。控除・特例の例としては「3,000万円特別控除」や「所有期間による税率の違い」などが挙げられます。
また、確定申告に必要な書類の準備や申告書の作成なども任せられるため、「手続きに不安がある」「税務署の説明がわかりづらい」という方にとっても、税理士は心強い存在です。
司法書士・行政書士:相続・登記の法的手続き担当
不動産の売却においては、所有権の登記手続きが関わってくることも多いものです。例えば相続不動産を売却する場合は、事前に相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。また、相続不動産でなくても、所有権移転の登記手続きが必要です。こうした手続きの専門家が司法書士と行政書士です。
司法書士は、所有権移転登記や抵当権抹消登記など、法務局への申請を代行する役割を担います。一方で、行政書士は、農地の転用許可や相続人の調査・書類作成など、行政手続きに強い専門家です。
「登記簿に親の名前が残っている」「農地を宅地として売りたい」などのケースでは、まずこの2つの専門家に相談してみるとスムーズに進められます。
弁護士:トラブル予防と交渉の心強い味方
例えば「相続人同士で意見が食い違っている」「買い主から契約内容にクレームが来ている」「不動産会社との関係に不信感がある」など、法的判断が必要な状況では弁護士への相談が効果的です。
弁護士は、契約書のチェックや法的リスクの洗い出しだけでなく、必要があれば交渉の代理人として動いてくれるため、相談しておくと気持ちの面でも安心できます。なお、「まだ明確なトラブルではないけれど、不安がある」といった段階でも、初回相談を利用してリスクを把握しておくと安心です。
土地家屋調査士・鑑定士:価値・境界の専門職
土地の境界があいまいな場合や、正確な面積・敷地条件が必要な場合には、土地家屋調査士に相談すると良いでしょう。隣地との境界線の確定や地積測量図の作成など、測量や物理的な確認作業を行う専門家が土地家屋調査士です。
また、不動産の公正な価値を第三者の立場で評価したい場合は、不動産鑑定士に相談するのが得策です。特に、相続財産の分割や裁判所・税務署へ提出する資料として「不動産鑑定評価書」が必要なときに、不動産鑑定士のサポートが役立ちます。
一般的な売却においては不動産会社の査定で十分ですが「より精緻な調査が必要」「トラブル回避のために法的根拠を持ちたい」などの場合は、土地家屋調査士などへの相談が必要になります。
ケース別:あなたの状況に合った相談ルート

不動産売却と言っても抱えている事情や背景は人それぞれです。誰に何を相談するべきか、状況によって大きく異なります。ここからは、よくある4つのケースに分けて相談すべき専門家や注意点をご紹介します。
ケース①:親から相続した実家を売りたい
親から相続した実家の売却では、「名義変更がまだ」「兄弟で共有している」「空き家になっている」などの複雑な要素が絡むことが少なくありません。まずは司法書士に相談して、相続登記(名義の変更)が必要かどうかを確認しましょう。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議が前提になるため、弁護士への相談を要することもあります。
また、長年空き家だった場合は、空き家バンクや自治体の相談窓口を利用するのも有効です。なお、売却益が出た場合は税金が発生するため、税理士にも早めに相談すると良いでしょう。
ケース②:離婚後の自宅を処分したい
離婚によって共有名義の不動産を売却する場合、注意すべきポイントは「名義」「住宅ローン」「持ち分割合」の3つです。住宅ローンが残っている場合は金融機関への確認を要します。契約内容によっては住民票の移動が契約違反になるなど、思わぬ落とし穴もあるため要注意です。
まずは不動産会社に査定を依頼し、現在の資産価値を把握しましょう。そのうえで、司法書士や弁護士に名義や分配方法を確認すれば、トラブルを未然に防げます。なお、売却で利益が出る場合は税理士への相談も忘れずにしておきましょう。
ケース③:マンションを売って戸建てに住み替えたい
「子どもが大きくなる前に戸建てに住み替えたい」「老後は郊外の平屋へ」など、住み替えを伴う売却では、「売るタイミング」と「買うタイミング」が重要です。資金計画の立て方や仮住まいの有無などを、最初の段階で不動産会社に相談することで、余裕のあるスケジュールを立てられます。
また、売却によって譲渡益が出る場合には、税理士に相談して特例の適用可否を確認しておくと良いでしょう。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関との調整や抵当権抹消手続きについて、司法書士のサポートが必要になります。
ケース④:親族と不仲、相続物件の扱いで揉めそう
相続した不動産を売却したいものの、他の相続人と意見が合わず進められないなどのケースでは、早めに弁護士へ相談するのが肝心です。感情のもつれやコミュニケーション不足などが原因で、相続の話し合いが長引いてしまうこともあります。
話し合いが済んだら、司法書士による名義変更や、不動産会社への売却依頼へ進みます。「トラブルが起きてから」ではなく、「起こりそうなときに先手を打つ」のが、円滑な売却のカギです。
不動産会社の選び方で成否が変わる

不動産売却の成功を大きく左右するのが、「どの不動産会社に依頼するか」です。価格設定、販売戦略、交渉力、契約時のサポートなど、それぞれ適切に対応するためには、不動産会社の協力が欠かせません。
しかし、「なんとなく地元の会社に頼んでしまった」「有名だから安心と思って決めた」というだけの理由で選んでしまうと、思ったようにことが進まないケースも起こり得ます。
“近所だから安心”は本当?判断基準を明確に
「地元だから安心」「大手だから間違いない」という思い込みではなく、自分の物件と目的に合う会社を選ぶことが何より大切です。
「家の近くにある不動産会社だから」「チラシがよく入っているから」という理由で不動産会社を選ぶ人も少なくありません。地域密着型の会社は地元の不動産市場に精通しているという強みがありますが、それだけで「安心」と判断するのは危険です。
売却活動を成功させるために必要なポイントは、マーケットの知識だけでなく担当者の対応力や販売戦略の幅、取引の透明性など多岐にわたります。また、店舗が近いからといって、必ずしも売却活動を積極的に行ってくれるとは限りません。
一方で、大手の不動産会社であっても、担当者の経験や売却の方針などがマッチしなければ、スムーズに売却活動が進まないこともあります。
不動産会社を選ぶときのチェックポイント5つ
不動産会社を選ぶ際は、次の5つのポイントを意識することで、失敗のリスクを大きく減らせます。
1. 実績と販売力があるか
過去の取引件数や、類似物件の売却経験があるかを確認しましょう。営業力や販路の広さもチェックポイントです。
2. 担当者は信頼できるか
親身に話を聞いてくれるのか、専門知識をわかりやすく伝えてくれるのかは重要です。押し売り感がある担当者は避けた方が無難と言えます。
3. 査定価格の根拠が明確か
査定額が極端に高すぎる場合は要注意です。高値で釣って専任契約を結ばせようとする不動産会社もあるため、根拠の説明をしっかり求めましょう。
4. 媒介契約の内容が適切か
「専任媒介」と「一般媒介」の違いを説明してくれるのか、契約内容に不利な条件が含まれていないかなどのポイントをチェックします。
5. 売却後のフォロー体制が整っているか
売却後の確定申告や登記、引き渡しの手続きまで含めてサポートがあるかどうかも確認しておきましょう。
複数の相談窓口を活用するのが“正解”の時代

一昔前までは、不動産会社に相談すれば売却は全て任せられるという時代でした。しかし、現代の不動産売却では、登記・税金・相続・ローンなど、専門分野ごとの対応が求められる場面が増えています。
全てを1カ所に任せきりにするのではなく、必要に応じて専門家の意見を聞きながら進めることが、トラブルや損失を防ぐうえで重要です。
「1カ所だけ相談」はむしろリスク
不動産会社に全てを任せた結果、「よくわからないまま話が進んでしまった」「後で税金が発生することを知って焦った」といった失敗例は少なくありません。不動産会社は売却の実務には強いものの、税務や法的手続きの専門家ではないからです。
「1カ所だけに相談して安心してしまうこと」が、かえってリスクになるケースは多いものです。必要に応じて、税理士・司法書士・弁護士・行政書士など、それぞれの専門家と連携しながら進めていくことで、不安のない取引が可能になります。
相談を“並列”ではなく“段階”で使い分ける
複数の専門家に相談する際は、同時に並列で相談するのではなく、「段階的に使い分ける」ことがポイントです。
例えば、売却の意志が固まっていない段階では、まず不動産会社に相談して相場感や売却の流れを把握するのが有効です。その後、売却が現実的になった段階で、司法書士に名義や登記関係を確認し、相続が絡む場合は行政書士や弁護士に意見を求めると良いでしょう。
売却後の税金が発生する場合には、税理士に節税対策や確定申告の内容を相談することが望ましいです。
このように、「今の自分のフェーズに合った専門家に相談する」というステップを踏むことで、効率的かつ正確に不動産売却を進められます。
相談費用が気になる人へ:無料と有料の違い

「専門家に相談したいけれど費用がかかるのでは?」という不安から、誰にも相談できず悩み続けてしまう方は少なくありません。しかし、不動産売却は情報不足や誤った判断によって数十万円〜数百万円の損につながることもあるため、適切なタイミングで専門家に相談することが何より大切です。
無料相談の種類と注意点
不動産の売却に関して無料で相談できる窓口は意外と多く存在します。代表的なのは、地域の不動産会社や市区町村の空き家相談窓口、宅建協会などの公的な無料相談です。
また、不動産会社による査定相談や販売戦略のアドバイスも、多くの場合無料で受けられます。最近ではオンラインやLINEなどでの簡易相談も増えており、以前よりも気軽に専門家へ相談できる環境が整っています。
ただし、無料相談には注意点もあります。あくまで初期的なアドバイスや一般論が中心で、個別の深い事情に踏み込んだ内容には対応しきれないこともあります。また、相談後に営業活動へ誘導されるケースもあるため、「話を聞くだけのつもり」であることを明確にしておくと良いでしょう。
有料でも価値ある専門家相談とは?
税理士・司法書士・弁護士など専門家への相談費用は、30分~60分単位の時間で発生するのが一般的です。一方で、初回無料相談を実施している事務所も多く存在します。事前に料金体系を確認し、納得できる範囲で依頼するのがポイントです。
有料相談を利用する最大のメリットは「自分のケースに合わせた具体的なアドバイス」を受けられることです。費用をかけることで、自分だけの判断による損失を未然に防げると考えれば、むしろ費用対効果の高い投資と言えるのではないでしょうか。
相談する前に準備しておくとスムーズになること

不動産売却の相談に行く際、「何もわからないまま相談しても大丈夫かな…」と不安に感じる人は多いものです。
もちろん、相談の段階で全てを把握しておく必要はありませんが、最低限の情報を整理しておくだけで相談の内容がより具体的になり、話がスムーズに進みます。また、家族や共有名義の関係者との事前確認もトラブル回避のためには重要です。
事前に用意しておきたい3つの基本情報
相談の際に以下の3点をあらかじめ用意しておくと、具体的なアドバイスを受けやすくなります。
①登記簿謄本(登記事項証明書)
物件の名義人や権利関係を確認するためには登記簿謄本が必要です。登記簿謄本は法務局やオンラインで取得できます。相続物件の場合は、不動産の名義が被相続人(元の持ち主)のままになっていることも多いため、売却前に確認しておきましょう。
②購入時の契約書・売買価格の情報
税金を計算するためには、売却する不動産の取得費を証明する必要があります。なお、どうしても取得費を証明できる書類が見つからない場合は、想定金額で税金を算出することも可能です。ただし、想定金額を用いると税金が高くなる可能性もあります。
③固定資産税の納税通知書
固定資産税の納税通知書には、税務署が算出した不動産の評価額が記載されています。不動産会社が査定をする際には、固定資産税の納税通知書を出すよう求められることが少なくありません。
福岡県内で不動産売却を進めるなら知っておくべき地域性
不動産の売却は全国共通の流れに沿って進められるとはいえ、地域ごとの市場環境や支援体制には大きな違いがあります。特に福岡県は、福岡市のような都市部と空き家が増加する郊外・農村部が混在しており、エリアによって売却戦略や相談先を変える必要があります。
空き家の多い地域とその売却のポイント
福岡県では、筑豊地域(飯塚市・田川市など)や筑後地域(久留米市・八女市など)などを中心として、空き家率が全国平均を上回る地域も増えています。高齢化や人口減少、都市部への若年層の流出により、実家や相続物件がそのまま放置されてしまうケースも少なくありません。
こうした地域での売却では、まず「現状のままで売れるのか」「リフォームや更地化が必要なのか」などを見極めることが重要です。地元に精通した不動産会社に相談し、需要のある売り出し方を見つけることが成功のカギになります。
また、行政から空き家が「特定空き家」に認定される前に動くこともポイントです。特定空き家に認定されると固定資産税が大幅に上がるリスクもあるため、早めに専門家へ相談・売却することをおすすめします。空き家バンクの活用や、補助金・解体費用の助成制度など、地域独自の支援制度にも目を向けてみましょう。
福岡市・北九州・久留米で相談できる公的窓口
福岡県内では、大都市圏を中心に不動産に関する相談を受け付ける公的な窓口が複数整備されています。売却を検討する際には、こうした機関を活用することで、費用を抑えながら正確な情報を得ることができます。
【福岡市】
福岡市役所は「空き家活用等支援制度」を設けており、空き家の売却や利活用に関する相談を無料で受け付けています。また、福岡県宅地建物取引業協会(福岡市博多区)には、不動産取引に関する無料相談窓口も開設されています。
【北九州市】
北九州市では「空き家対策総合相談窓口」を設置しており、売却・賃貸・解体などを含む空き家の利活用について幅広くサポートしています。市役所の建築指導課などを通じて相談が可能です。
【久留米市】
久留米市では、空き家対策係が窓口となって、空き家バンクの運営や相談受付を行っています。特に相続後に手続きが進んでいない物件など、売却の前段階からアドバイスをもらえます。
これらの公的機関では、民間の不動産会社とは違い、「すぐに売却しましょう」と急かすことがなく、中立的な立場でアドバイスしてもらえるのが特徴です。
不動産売却の相談ならグラングッド不動産へ
福岡県内で不動産の売却を検討しているなら、グラングッド不動産にご相談ください。グラングッド不動産は、福岡で地域密着型の強みを持つほか、丁寧で親身な対応をご評価いただいています。「何から始めたら良いかわからない」「売却後の手続きが不安」といった初めての方でも安心してご相談いただけます。
当社では、住宅ローンや税金、火災保険など、売却後のライフプランまで見据えたサポートを得意としており、お客様一人ひとりの状況に応じた資金計画やアドバイスを提案しています。相続や資産整理、住み替えなど、複雑な背景を伴う売却にも柔軟に対応可能です。
さらに、購入・売却後のアフターサポートにも力を入れており、不動産取得税や固定資産税の手続き、近隣トラブルの対応、さらには将来の相続・贈与・資産売却まで、生涯にわたる相談相手としてご対応します。
「相談したらすぐに契約を迫られるのでは…」という不安を感じている方にも、押し売りのないスタンスで、気軽に話せるパートナーとして信頼されています。福岡エリアで納得のいく不動産売却を目指すなら、ぜひグラングッド不動産を相談先の一つとしてご検討ください。
まとめ
不動産売却は人生で何度も経験することのない大きな決断です。「誰に相談すればいいのか」「手続きはどう進めるのか」など、多くの不安を感じるのは当然のことです。
この記事では、売却の流れやケース別の相談先、福岡県内の地域特性に合わせたポイントまでを解説しました。最適な相談相手を見極め、段階ごとに専門家の力を借りることで、安心して売却を進められるでしょう。