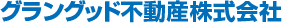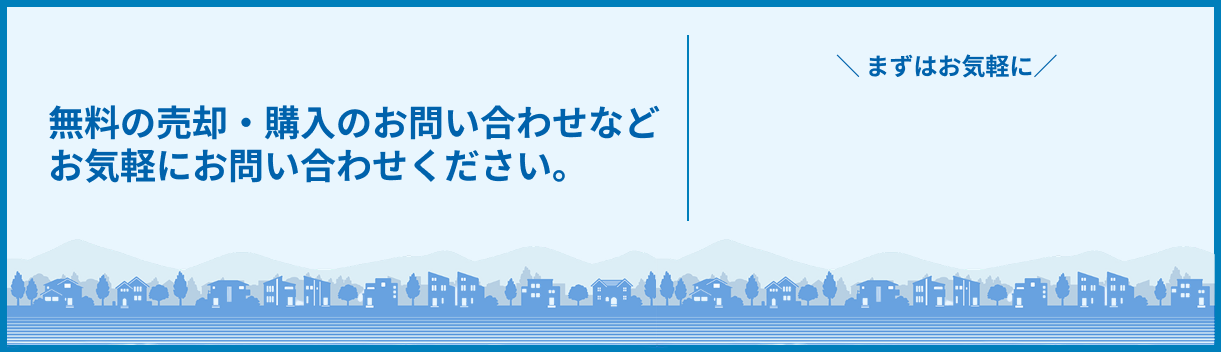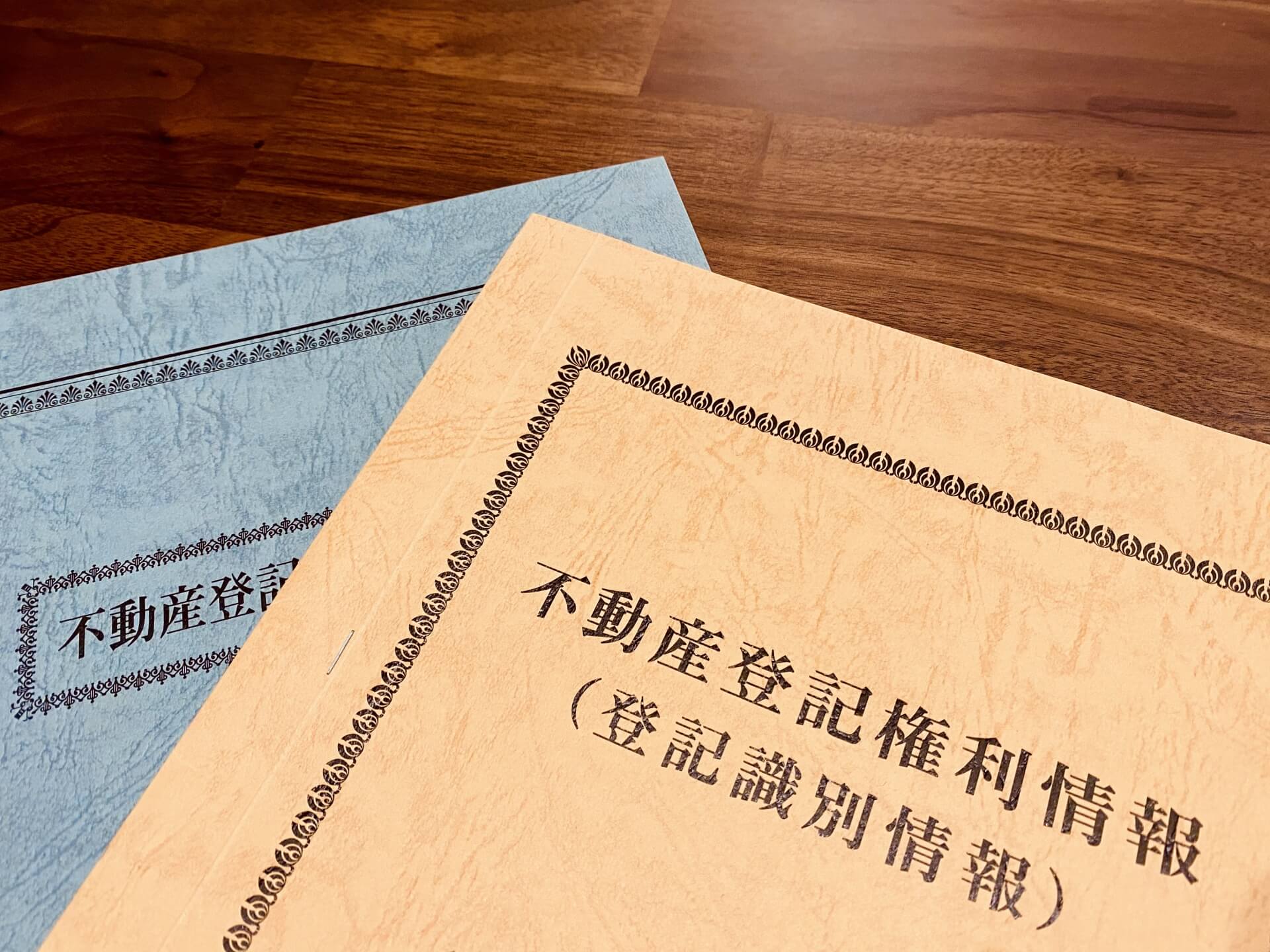新築一戸建てにかかる「費用」の基本を押さえよう
新築一戸建てを購入する際、「建物の価格=総費用」と考えてしまう方も多いかもしれません。しかし実際には、土地代、建築費、諸費用、住宅ローン関連費用など、さまざまな出費が発生します。
さらに、地域や家の仕様によっても金額は大きく異なるため、気づきにくい支出が家計を圧迫することもあるため要注意です。
土地価格の相場とエリア差
土地代は、新築一戸建ての総費用に大きく影響する要素の一つです。土地代の相場はエリアによって大きく異なります。土地の広さによるものの、例えば都市部やその郊外の人気エリアでは1,500万円以上かかることがめずらしくありません。しかし、地方の郊外であれば数百万円台から購入できるケースもあります。
また、同じ市区町村内でも、駅からの距離や周辺環境、接道条件によって土地の価格は変動します。さらに、変形地や傾斜地などは割安に見えることもありますが、購入後に造成費がかかったり、建築制限があったりするケースも多いため要注意です。
建物の建築費と標準仕様の目安
建物の建築費は、工法や建物の仕様、建物の広さなどによって異なります。なお、一般的には、「建売住宅」よりも「注文住宅」の方が費用は高くなります。ただし、注文住宅は間取りやデザインの自由度が高く、自分たちの理想を反映しやすいのがメリットです。
広さや間取りによって変わりますが、建物本体の工事費はおよそ1,000万円~3,000万円程度と考えておきましょう。ただし、グレードの高い設備や自然素材などを取り入れると、追加費用が発生することもあります。
坪単価だけを見るのではなく、「どの仕様が標準で、オプションに当たるのは何か」を確認しておくことが、予算オーバーを防ぐためのポイントです。
諸費用の内訳(登記・仲介手数料・税金など)
建物と土地の費用以外にもさまざまな「諸費用」がかかりますが、いくらくらいなのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。諸費用は物件価格の5%~10%ほどが目安とされており、金額にすると数十万円から数百万円にのぼることもあります。
主な諸費用は以下の通りです。
- 登記費用
所有権登記や抵当権設定登記にかかる登録免許税、司法書士報酬など。
- 仲介手数料
不動産会社を介して土地や建物を購入した場合に支払う手数料(物件価格の3%+6万円が上限)。
- 税金関係
不動産取得税、印紙税、消費税(建物のみ)などが該当します。
- 保険料やローン関連の費用
火災保険、地震保険、住宅ローンの保証料や融資手数料など。
また、引っ越し費用や家具家電の購入費も意外と大きな出費になります。見積もりの段階で、これらの諸費用も含めて総額を把握しておくことが、安心して家づくりを進めるためのポイントです。
新築の一戸建て「項目ごとの費用相場」を徹底解説

新築一戸建てを建てる際、特に注意を要するのが「建築費」の中身です。建築費の内訳は「本体工事費」「付帯工事費」「外構工事費」など複数の費用に分かれており、それぞれの項目ごとに相場や金額が異なります。
本体工事・付帯工事・外構工事の目安
本体工事費は、家の柱や壁、屋根、床など住宅本体を構成する基本的な構造と内装、設備の標準仕様を施工するための費用です。総建築費のうち約70%~80%を占めることが多く、例えば30坪~35坪程度の住宅であれば、1,500万円~2,500万円程度が相場とされています。
付帯工事費には、仮設工事(足場の設置など)や電気・ガス・水道の引き込み、地盤改良、解体工事、エアコン取り付けなどが含まれます。土地の状態によって金額は変わりますが、総額の10%~20%前後が目安です。
外構工事費は、門扉、フェンス、カーポート、庭、玄関アプローチなど敷地まわりの整備にかかる費用です。これもグレードや広さによって大きく変わりますが、一般的には50万円~200万円程度の費用がかかります。
なお、地盤改良や外構工事の費用は後から追加されるケースも多いため、契約前によく確認しておくことをおすすめします。
設備グレードと費用アップの関係
建物の構造や広さに加えて、費用に大きな影響を与えるのが「住宅設備のグレード」です。特にキッチン・浴室・トイレ・洗面台などの水回り設備は、仕様の違いによって費用が大きく変動します。
例えば、キッチンでは食洗機やIHコンロ、タッチレス水栓などのオプションをつけると費用が高くなります。浴室についても、浴室乾燥機やミストサウナなどの機能をつけると、20万円~50万円程度費用が高くなるため、事前確認が必要です。
さらに、フローリングや壁紙、断熱材、サッシなど内装・建材の素材選びも費用が変わるポイントです。無垢材などの自然素材を取り入れると、見た目や機能性は良くなるもののコストが上がります。
想定外の出費を抑えるコツは、「どこにこだわり、どこで節約するか」を決めることです。例えば、リビングなど人目に触れる空間はグレードを上げて、リビング以外の居室は標準仕様にするなどの工夫をすると良いでしょう。
押さえておきたい「維持費」とメンテナンスコスト

新築一戸建ての購入後も、家に住み続けているとさまざまな費用がかかります。住宅ローンの返済だけでなく、税金や保険、修繕などの維持費などが家計を圧迫することは多いものです。
固定資産税・都市計画税の目安
不動産を所有している限り、固定資産税と都市計画税を毎年支払うことになります。固定資産税は土地や建物の評価額をもとに算出され、税率は原則1.4%です(自治体によって異なる場合があります)。都市計画税は都市計画区域内の物件にかかる税金で、0.3%が上限です。
新築住宅には固定資産税の軽減措置が適用されるケースもあります。例えば、120㎡までの住宅部分については、新築から3年間(3階建て以上の耐火構造なら5年間)、固定資産税が半分まで軽減される制度があります。
ただし、土地の広さや建物の構造、エリアによって評価額は大きく異なるため、事前に評価額に関する情報などを確認しておくと安心です。
火災保険・地震保険の選び方
住宅ローンを利用する場合は、一般的に火災保険への加入は必須とされます。火災保険の保険料は、補償範囲や保険期間によって大きく変動します。
なお、地震保険は基本的に火災保険の特約になっており、加入は任意です。地震保険単体での加入はできません。また、地震保険は保険金の支払い要件も「厳しい」と感じる人が多い内容になっています。
地震が起きれば簡単に使えるというものではありませんが、いつ大きな地震が起こるかは正確な予想が難しいものです。リスクが高いエリアでは特に、前向きに考えておく方が良いでしょう。
修繕・リフォームにかかる費用
新築であっても、年数の経過とともに定期的な修繕・メンテナンスは必要です。特に給湯器や水回りの設備などは、10~20年のスパンでリフォームが必要となるケースも多くなっています。
トイレやキッチンなど水回りの設備交換には、1カ所あたり30万円以上かかることもあります。そのほか、例えば外壁塗装は15年ごとに約100万円~150万円、屋根の葺き替えは100万円~200万円程度が一般的な目安です。
また、住宅のグレードや使用している素材によってもメンテナンス費用には差が出ます。将来的な大規模リフォームに備え、毎月決まった額を「修繕積立」として積み立てておくと、いざというときに安心です。
新築一戸建ては減税制度を利用してお得に購入しよう
新築一戸建ての購入には高額な費用がかかりますが、減税制度を活用すれば、実質的な負担を軽減できます。制度のなかには期間限定のものや基準が設けられているものもあるため、事前の確認が必要です。
住宅ローン減税の最新情報
住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合は、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」を活用することで、所得税や住民税の一部が控除されます。
2025年時点での住宅ローン減税制度の主な概要は以下の通りです。なお、以下の条件等は税制改正等によって変更される可能性があるので、国土交通省のホームページで確認することをおすすめします。
- 控除内容
年末における住宅ローン残高の0.7%を13年間控除
- 控除対象となる借入残高の上限
住宅の性能により異なる(省エネ基準適合住宅で3,000万円、長期優良住宅または低炭素住宅で4,500万円)
- 対象となる住宅の条件
床面積が50㎡以上(2024年末までに建築確認を受けていれば40㎡以上でも対象)
- 所得の条件
合計所得が2,000万円以下の人が対象
2025年時点では省エネ性能を備えた住宅への優遇が強化されており、「住宅の性能による控除枠の差」が大きくなっています。ローン控除を最大限に活用するためには、住宅の性能にも目を向けて建築プランを決めることが重要です。
また、申請手続きには確定申告が必要です。入居した翌年に税務署で手続きする必要があります。なお、会社員でも自分で申告する必要がある点に要注意です。
想定外の追加費用を防ぐための注意点

新築一戸建ての購入にあたっては、当初の見積もりにはなかった「追加費用」が後から発生するケースも少なくありません。想定外の支出を防ぐためには、契約書や見積書の内容を事前に確認することが重要です。
契約書・見積もりで確認する項目
新築住宅を建てる際は、ハウスメーカーや工務店と交わす「工事請負契約書」や「見積書」に、何があって何がないのかを明確にすることが最も重要です。以下のポイントは事前確認が必須と言えます。
- 地盤調査・地盤改良費の有無
地盤の強度によっては、追加で数十万円~100万円程度かかることも。
- 付帯工事・外構工事の範囲と内容
駐車場、塀、アプローチ、庭などが別見積もりになる場合があります。
- オプション項目の詳細と金額
キッチンや浴室のグレードアップ、照明、カーテン、エアコンなど。
- 諸費用の取り扱い(登記費用、火災保険料、ローン手数料など)
「別途精算」となっている場合は、後からまとまった金額になることも。
また、見積書は「一式」表記ではなく、項目ごとに単価と数量が書かれているか確認することが大切です。不明点がある場合は遠慮せず質問し、口頭ではなく書面での回答を求めましょう。
トラブルへの対処と相談窓口
万が一、引き渡し直前に高額な追加費用を請求されたり、契約書に記載のない請求が発生したりした場合には、見積書や契約書と照合し、本当に追加請求が正当なのかを確認しましょう。施工内容や数量の相違がある場合は、再見積もりや再説明を求めるのが基本です。
それでも納得できない場合や、対応が不誠実と感じた場合には、第三者機関への相談が有効です。以下のような窓口が利用できます。
| 住宅リフォーム紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) | 国土交通省の支援を受けた中立的な相談窓口です。無料で専門家に相談できます。 |
| 消費生活センター(各自治体) | 契約内容が不当であったり説明不足が疑われたりといった場合に相談できます。 |
| 弁護士や建築士などの専門家 | 契約書の内容確認や法的アドバイスを受けたい場合に有効です。 |
なお、トラブルが起きた際は記録(メール・請求書・契約書など)を残すことが非常に重要です。
まとめ
新築一戸建ての購入には土地代や建築費だけでなく、登記費用や税金、保険料など多くの費用がかかります。なお、設備グレードや外構工事、地盤改良といった項目でも費用は大きく変動するため、契約前の見積もり確認が重要です。
一方で、減税制度を活用すれば負担の軽減も可能です。想定外の出費を避けるためには、契約・工事前の確認と正確な情報収集が重要になります。
福岡で新築一戸建てを検討中ならグラングッド不動産へ
新築一戸建ての費用を正確に把握し、納得のいくマイホームを実現するには、信頼できるパートナーの存在が欠かせません。福岡で住まい探しをするなら、「グラングッド不動産」にぜひご相談ください。
物件探しから住宅ローン、税金、保険、インテリアまで一括でシミュレーションできるのが特長で、グラングッド不動産では、引っ越し後の生活全体を見据えた資金計画が可能です。
また、家の購入後もアフターメンテナンスや将来の相続・売却相談まで一貫してサポートしますので、家の購入が初めての方でも安心して一歩を踏み出していただけます。