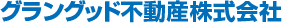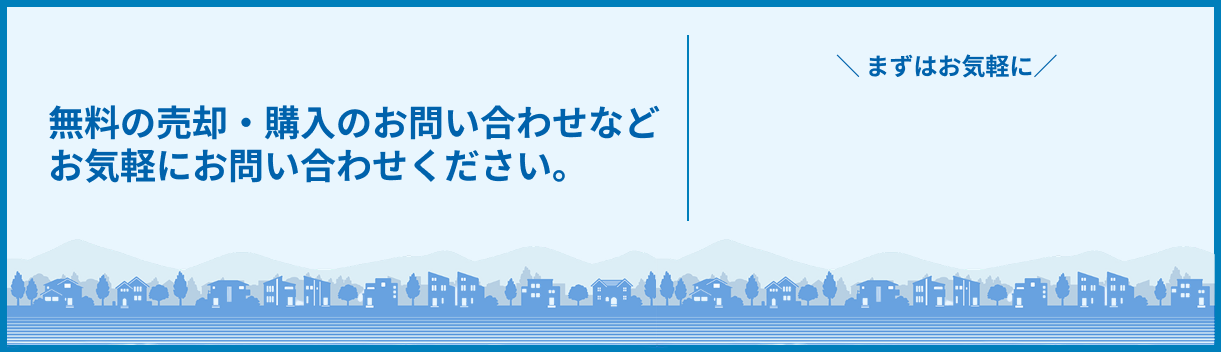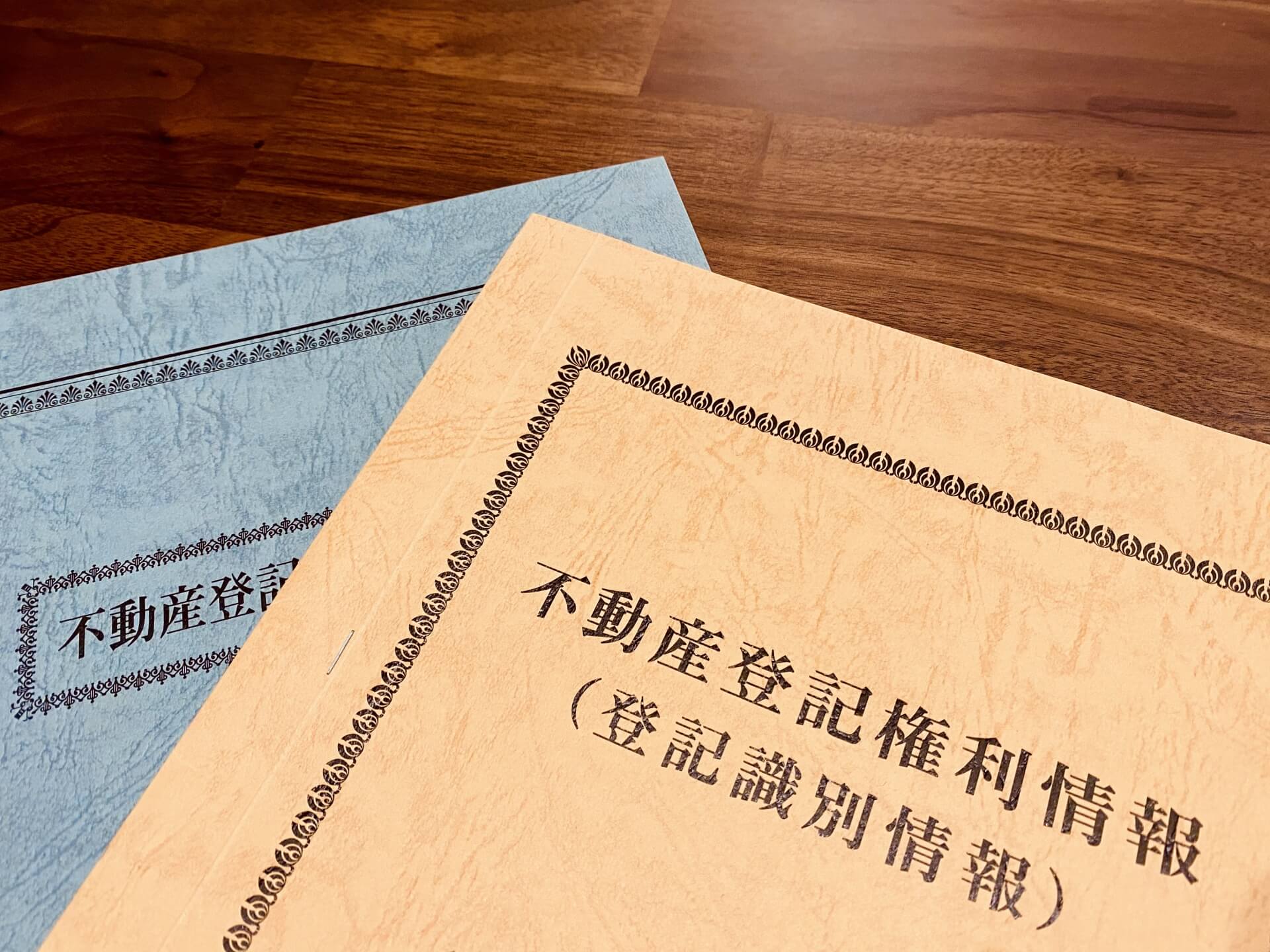個人間で不動産売買はできる?増える「直接取引」の背景
不動産の売買といえば、不動産会社に依頼して進めるのが一般的です。しかし近年では、親族や知人、隣地所有者などとの取引において、不動産会社の仲介を受けない「個人間売買」も増えています。
なぜ仲介を通さない売買が増えているのか?
個人間売買を選ぶ人が増えている背景には、大きく分けて3つの理由があります。
1つ目は、仲介手数料などの費用を抑えたいというニーズです。不動産会社に仲介を依頼すると、売買価格の3%+6万円(別途消費税)の仲介手数料が発生します。
数百万円〜数千万円規模の取引では、仲介手数料だけで数十万円以上の金額になるため、「できるだけ安く済ませたい」という人が増えています。
2つ目は、親族や知人など、信頼関係のある人が取引相手であることです。例えば、親から子への持ち家の売却、隣地を所有する人との土地取引など、相手がもともと顔見知りであれば、「わざわざ不動産会社の手を借りなくてもいい」と考える人も少なくありません。
3つ目は、情報収集や契約書の作成支援ツールが充実してきたことです。2025年時点では、ネット上に不動産売買契約書のテンプレートが無料で多数公開されているほか、登記に関する解説記事や動画も多くなっています。このような環境の変化が、「専門家に頼らなくてもできるのでは?」という意識を後押ししています。
個人売買が選ばれるケースとは?実例を交えて紹介
実際に個人間取引が選ばれるケースとしては、以下のような例が見られます。
親族間での住宅の売買
例えば、実家に住み続けている子どもが相続の代わりに親から家を買い取るといったケースです。贈与ではなく売買にすることで、税務リスクを避けつつ、手続きも簡素化できます。
隣地の所有者同士の売買
隣地の空き地を買い取りたい、あるいは共有地を解消したいといった場合に、直接話し合って取引を進めることがあります。
知人から築古物件を安く購入する場合
例えば郊外では、古くなった空き家を知人から破格で譲り受けるといったケースもあります。このような取引では、取引価格が低い一方で仲介手数料の負担が大きいため、「不動産会社を介したくない」と考える人も多いものです。
契約書は雛形だけで大丈夫?リスクと注意点を徹底解説

不動産売買の契約書は、取引の条件や責任を明確にするための重要な書類です。個人間売買でよく使われる「契約書の雛形」は便利な反面、そのまま使うと内容が不十分なこともあるので要注意です。
特に、親族間や知人との売買では、「信頼できるから大丈夫」と思っていても、後になって認識の違いからトラブルに発展するケースもあります。ここからは、雛形を使用する際の注意点や、契約書に記載すべき基本項目、特約の活用法などを解説します。
ネットのテンプレートを使うときの注意点
不動産売買契約書の雛形は、インターネット上で多くのテンプレートが公開されており、無料でダウンロードして使用可能です。個人売買を考えている方にとって、これらのテンプレートは「手軽に契約書を作成できるツール」として重宝されがちです。
しかし、テンプレートを利用する際にはいくつかの注意点があります。まず、雛形の内容が「自分の取引内容に合っているか」を確認する必要があります。
例えば、売買対象は土地だけなのか建物も含むのか、抵当権は付いているのか、境界線の確認は済んでいるのかなどのポイントです。状況に応じて必要な条項や表現は変わるため、汎用的な雛形をそのまま使うと重要なポイントが抜け落ちてしまうリスクもあります。
また、出所の不明なテンプレートの使用も避けた方が無難です。出所が分からないものは古い法令に基づいたものだったり、商用目的の誤った内容が含まれていたりといったこともあります。弁護士会や宅建協会など、公的機関が提供するテンプレートを選ぶことが大切です。
契約書に必ず記載すべき10の基本項目
不動産売買契約書を作成する際には、最低限押さえておくべき基本項目があります。これらの内容がきちんと記載されていないと、万が一のトラブル発生時に“言った・言わない”の争いになり、法的にも不利になる可能性があるため要注意です。
- 物件の表示(所在地・地番・種類・構造など)
- 売買代金の金額および支払い方法(手付金・残代金の支払い時期と方法)
- 所有権移転の時期(代金支払いと同時か、別の日か)
- 引き渡し時期および方法(鍵の受け渡し、現況引き渡しなど)
- 公租公課の清算方法(固定資産税などの清算ルール)
- 実測と登記簿面積の差異に関する取り決め
- 担保権の抹消に関する取り決め(抵当権など)
- 契約不適合責任の有無と内容(瑕疵があった場合の対応)
- 危険負担の取り扱い(引き渡し前に物件が損傷した場合の対応)
- 違約・解除に関する条件(契約解除の方法と損害賠償の規定)
上記の項目は、いずれも「当事者間の責任範囲」を明確にするものです。特に、個人間売買ではお互いに専門知識がない場合も多いため、曖昧な表現を避けて、具体的かつ明確に記載するよう心がけましょう。
特約を活用すればトラブルを回避できる
不動産売買契約書には、前項で解説した基本項目に加えて「特約条項」を追加できます。特約とは取引の内容や事情に応じて、個別に取り決めを記載する任意の条項です。個人間売買では、標準的な契約書では対応しきれない細かな事情も生じやすいため、特約の記載がトラブル防止に役立ちます。以下のような特約は特に有効です。
- 親から子への売却で、相続登記が未完了のとき
「売り主は引き渡しまでに自己名義への相続登記を完了させる」旨を特約で明記する。
- 売買後もしばらく売り主が居住を継続する場合
「〇月〇日まで無償で居住を認める」など、期限付きで明示する。
- 古家付き土地で、建物解体は買い主が行うケース
「建物解体および滅失登記は買い主負担とする」などの特約が必要です。
特約を設けておかないと、「聞いていなかった」「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いが起こりがちです。テンプレートには特約の欄が省略されていることも多いため、契約書を作成するに際は、具体的な文言で特約を加える工夫が必要です。
契約書を自作するなら?作成から締結までの完全ガイド

不動産の売買契約書については、ネット上のテンプレートを活用すれば、ある程度のフォーマットは整えられますが、実際には「何から手をつければいいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
契約書を自作する際に必要な準備や手順、揃えておきたい書類、記載ミスを防ぐためのチェックポイントなどを整理してご紹介します。
契約書作成の流れと必要な準備
契約書を自作するには、まずは取引の全体像を整理して、情報を揃えることから始める必要があります。以下は契約書作成から締結までの基本的な流れです。
1.売買の条件をすり合わせる
売買価格、引き渡し日、代金の支払い方法、設備の引き継ぎなど、双方の希望をすり合わせます。
2.物件情報を確認する
登記簿謄本などを取得し、土地や建物の正確な情報を確認します。登記簿上の名義人が誰か、抵当権などの権利関係がないかも要チェックです。
3.雛形を基に契約書を作成する
信頼できるテンプレート(弁護士会や宅建協会などが提供しているもの)をベースにして、必要に応じて特約や条件を加筆・修正します。
4.内容の最終確認と調整
特に金額・日付・名義などは細かいミスが起きやすいため、ダブルチェックしましょう。
5.署名・押印と収入印紙の貼付
売り主と買い主の双方が署名・捺印し、印紙税額に応じた収入印紙を契約書に貼り付けて割印をします。
6.契約書の保管と提出
契約書は2通作成し、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつを保管します。契約書は登記や税務申告にも使用するため、紛失しないように注意が必要です。
書類リストと入手方法
契約書の作成や登記に必要な書類は、売り主と買い主で若干異なります。主な書類とその入手先は以下の通りです。
売り主が用意する書類
- 登記簿謄本(法務局またはオンラインで取得)
- 固定資産税納税通知書(市区町村役所)
- 印鑑証明書(市区町村の窓口/マイナンバーカードでコンビニ取得も可)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 登記識別情報(権利証)
買い主が用意するもの
- 実印と印鑑証明書
- 本人確認書類
- 手付金
自作派のための契約書チェックリスト
自作の契約書は自由度が高い反面、記載漏れや形式不備が原因で後に無効と判断されるリスクもあります。以下は、契約書を作成する際に確認しておきたいチェックリストです。
□ 売り主・買い主の氏名・住所・押印が正しく記載されている
□ 物件の所在地・地番・面積などが正確に反映されている
□ 売買代金の金額・支払い方法・支払日が明確に記載されている
□ 所有権移転と引き渡しの時期が明示されている
□ 固定資産税などの精算方法が記載されている
□ 契約不適合責任(瑕疵があった場合)の範囲が明示されている
□ 必要に応じて特約が反映されている
□ 日付の整合性が取れている
□ 収入印紙の金額が正しく、割印がある
□ 双方の契約書が各1通ずつ作成・保管されている
なお、少しでも不安がある場合は、司法書士や不動産会社に相談して内容を確認してもらうと良いでしょう。
見落とし注意!契約書以外で必要な手続きと税務知識

不動産の個人間売買では、契約書の作成に意識が行きがちですが、実際にはその後の手続きや税務処理も非常に重要です。
たとえ契約書の内容が完璧でも、登記や税金の処理に不備があると、法的なトラブルや余計な出費につながることもあります。ここからは、契約後に必要な登記の手続きや関連費用、関連する税金の種類と節税のポイント、住宅ローン利用時の注意点などについて解説します。
登記手続きの進め方と必要費用
不動産の売買が完了したら、買い主は「所有権移転登記」の手続きを行う必要があります。所有権移転登記とは、法務局に対して「この不動産の所有者が変わりました」と正式に届け出る手続きのことです。
登記をしないと、不動産の所有者としての権利を第三者に主張できないため、売買契約の締結後は速やかに登記を進めることが基本です。登記手続きは、通常は司法書士に依頼して進めます。依頼した場合の費用は以下の通りです。
- 所有権移転登記の登録免許税
通常は固定資産税評価額×2.0%、軽減措置があれば0.3〜0.4%
- 司法書士報酬
3万円~5万円が目安
- その他必要書類の取得費用
登記簿謄本、印鑑証明書など(一つの書類につき数百円程度)
また、売り主側に住宅ローンの残債がある場合は、抵当権抹消登記の手続きも必要です。この手続きも司法書士に依頼できますが、別途1万円前後の費用がかかることを想定しておきましょう。
税金の種類と節税のポイント
個人間で不動産を売買する際には、いくつかの税金が発生します。なかには、契約書を交わすだけでも課税対象となるものがあるため、事前に把握しておくことが重要です。
印紙税
売買契約書に記載の金額に応じて課税されます。契約書1通につき、売り主と買い主が折半で負担します。例えば、売買代金が1,000万円の場合は、1万円の印紙税が必要です(2025年時点の税制に基づく)。
登録免許税
所有権移転の登記をする際に課税されます。軽減措置の対象となれば、評価額の0.3%が目安です。
譲渡所得税(売り主側)
不動産を売却して利益が出た場合に課税されます。マイホームを売却した場合は、3,000万円の特別控除などの優遇措置を活用可能です。
不動産取得税(買い主側)
不動産を購入した後に課税される地方税で、基本的な税額は固定資産税評価額×3.0%です。条件を満たせば軽減措置を受けられることもあります。
節税のポイント
契約書に記載する金額を市場の相場に近づけることで、「みなし贈与課税」などの余計な課税リスクを回避できます。特に親族間の売買では、相場より安い金額にしがちなため要注意です。また、必要経費や取得費を正確に把握することで、譲渡所得税を抑えられます。過去の登記費用・リフォーム費・仲介手数料なども控除対象です。
そのほか、適用できる軽減措置を確認すると良いでしょう。マイホーム取得の特例や住宅用家屋証明などを活用すれば、税額が大きく変わる場合もあります。
住宅ローンを使いたい場合の注意点
個人間売買でも、買い主が住宅ローンを利用することは可能です。一方で、いくつかのハードルがあることを理解しておきましょう。
まず、金融機関の多くは「重要事項説明書の提出」や「売り主が宅建業者であること」を住宅ローンの利用条件としています。また、金融機関からは以下のような書類を求められることがあります。
- 不動産売買契約書(署名・押印済み)
- 登記簿謄本
- 物件の写真
- 所有権移転後の登記計画書(司法書士作成)
- 売り主・買い主双方の本人確認資料
住宅ローンを使いたい場合は、事前に対応可能な金融機関を調べておくことが重要です。
契約内容はこう書く!実際のシーン別トラブル防止のコツ

契約書を自作すると「実際の状況に合っていなかった」というだけで思わぬトラブルが発生することがあります。特に、親族間や法人との売買など、特殊な事情を含む取引では、「その状況ならではの内容」を契約書に記載することが必要です。
親子・親戚間の売買で注意すべきポイント
親族間の売買では、信頼関係があるからこそ「そこまで細かく決めなくてもいい」と思いがちです。しかし、価格設定や支払い方法、登記のタイミングを曖昧にすると、税務署から贈与とみなされて課税されるリスクがあります。
特に注意したいのは「相場とかけ離れた価格」です。例えば、市場価格2,000万円の住宅を1,000万円で売ると、差額の1,000万円が「贈与」とみなされ、贈与税が課されることがあります。そのため、契約書には次のような内容を明記しましょう。
- 価格の妥当性(可能であれば近隣の相場や査定資料を添付)
- 支払い方法とスケジュール(現金一括か、分割か)
- 所有権移転の時期
- 税務上の相談を受けた旨(可能なら税理士などの関与を示す)
また、相続登記が終わっていない場合は、「契約締結までに相続登記を完了させる」旨の特約を追加しておくと安全です。
法人と個人が売買する場合の契約書記載例
売り主・買い主のいずれかが法人である場合、契約書に記載すべき内容や確認すべき事項が変わります。例えば、自営業者が個人所有の土地を法人に売却するケースでは、税務上の取引関係や登記名義の整合性が重要です。このようなケースでは、以下の点を契約書に盛り込むと良いでしょう。
- 取引当事者の正式名称(法人名+代表者名、法人の登記簿記載住所)
- 目的(「事業用資産として取得」など)
- 決済方法(役員貸付による支払い等の場合はその旨を明記する)
- 登記名義人の変更と法人登記との関係性
また、法人が買い主の場合は社内の稟議や決裁フローに時間がかかることもあります。「契約締結日から〇日以内に決済・引き渡しを行う」といった、柔軟性のある日程を設定することも視野に入れると良いでしょう。
「分割払い」や「引き渡し後の居住」など、特殊条件の記載方法
個人間売買では「一括ではなく分割払いにしたい」「引き渡し後もしばらく売り主が住み続ける」といった、特殊な条件が含まれることがあります。こうした内容は、口約束で済ませるのではなく、必ず契約書に明記しましょう。
例えば、分割払いの場合の記載例は以下の通りです。
「買い主は本契約に基づき、売買代金〇〇円を以下の通り分割で支払うものとする。第1回支払い:〇〇〇〇年〇月〇日〇〇円、第2回…」
この際、支払いが滞った場合の違約条項も併せて記載しておくと安心です。
また、引き渡しが終わった後も売り主が住み続けることを認める場合には、以下のような内容を加えましょう。
「売り主は、本物件の所有権移転後も〇〇〇〇年〇月〇〇日まで無償で当該建物に居住できる」
住み続ける期間中に発生する光熱費や修繕費の負担者についても、明確に記載しておくと、後の誤解を防げます。内容に自信がない場合は、司法書士や弁護士にチェックを依頼するのも有効です。
自分でやるか?プロに頼むか?判断基準と費用感

不動産の個人間売買では、自作で進められる部分と、専門家の力を借りた方が良い部分とがあります。無理をしてすべてを自力で行うよりも、必要に応じてプロの手を借りる方が、ミスやトラブルを防げるでしょう。
自作のメリットと限界を整理する
不動産売買契約書を自作する最大のメリットは費用を抑えられることです。契約書を自作すれば仲介手数料や司法書士報酬が発生しないため、数万円~数十万円のコスト削減につながることもあります。ただし、自作には限界もあります。特に以下のようなリスクに要注意です。
- 法的に不備のある契約内容になってしまう可能性
- 特殊な事情(相続登記未了、抵当権付き、法人絡み)に対応しきれない
- 登記や税金に関する手続きの見落としが起こりやすい
- 後日のトラブル時に「契約書の内容が曖昧だった」と不利になるおそれ
専門家に依頼するといくらかかる?費用の目安
不動産取引に関わる専門家には、主に司法書士・税理士・行政書士・弁護士・不動産会社などがあり、それぞれに役割と費用相場があります。以下は、おおよその費用目安です(地域や内容により変動します)。
| 依頼内容 | 費用相場 | 備考 |
| 契約書の作成サポート | 3万~5万円 | |
| 所有権移転登記 | 3万~6万円
登録免許税が別途必要 |
抵当権抹消の処理は別途有償 |
| 税務アドバイス | 1万~3万円 | 節税や贈与税に関する相談 |
| 法律相談 | 30分5,000円など |
※上記の費用は目安です。
なお、地元の不動産会社を通せば、これらの専門家と連携したサポートをワンストップで受けられるケースもあります。費用が一括化されて分かりやすく、トラブルが起きた際にも安心です。
「この場合は専門家に相談すべき」3つのチェックポイント
自作するかとプロに依頼するか迷ったときは、次の3つのポイントに当てはまるかどうかで判断すると良いでしょう。
1.契約に特殊な条件や関係性がある場合
親族間売買や法人との取引など、通常の個人間売買でない場合は、専門家の目でリスクを整理した方が安全です。
2.登記・税金の手続きに自信がない場合
「固定資産税評価額って何?」「登記ってどうやるの?」などの疑問があるのなら、プロである司法書士や税務の専門家に相談した方が、手間も時間も削減できます。
3.将来的なトラブルを極力避けたい場合
たとえ今は円満な関係であっても、相続や離婚などで揉め事に発展する可能性があるなら、法的に抜けのない契約書を作成しておく方が安心です。
それでも不安なときは?グラングッド不動産にお任せください
契約書を自作しようと頑張ってみたけれど、「やっぱり不安が拭えない」「専門家に一度確認してもらいたい」そんなときは、福岡で地元密着型の不動産会社「グラングッド不動産」にご相談ください。
グラングッド不動産は、個人間売買の相談はもちろん、登記や税務、資金計画に関するアドバイスまでトータルでサポート。さらに、提携する司法書士や税理士との連携も可能なため、契約書の作成や登記に関する疑問もワンストップで解決できます。
また、購入後のフォロー体制も充実しています。固定資産税や不動産取得税の手続き、相続や贈与、資産売却など、将来の不動産に関するお悩みにも丁寧に対応しています。
「家を買って終わり」ではなく、「住んでからが本当のお付き合い」と考えているのが、グラングッド不動産の信念です。
住宅ローンの使い方に迷っている、契約書の内容が本当に適切か判断できない、不動産のことで第三者の意見を聞きたい、そんなときは、地域事情に精通した私たちにお気軽にご相談ください。あなたの安心取引を最後までサポートします。
まとめ
個人間で不動産を売買する際には、契約書の作成や登記、税金の知識まで幅広い対応が求められます。テンプレートも活用できますが、取引内容に応じた文言の調整や特約の追加をしないと思わぬトラブルを招くこともあるでしょう。
契約書の自作には費用を抑えられるメリットがありますが、専門家のサポートを受けるとより安心です。不安を感じたら、福岡の不動産市場に精通した「グラングッド不動産」にぜひご相談ください。安心して取引を進めるための最適なパートナーとしてサポートいたします。