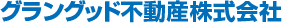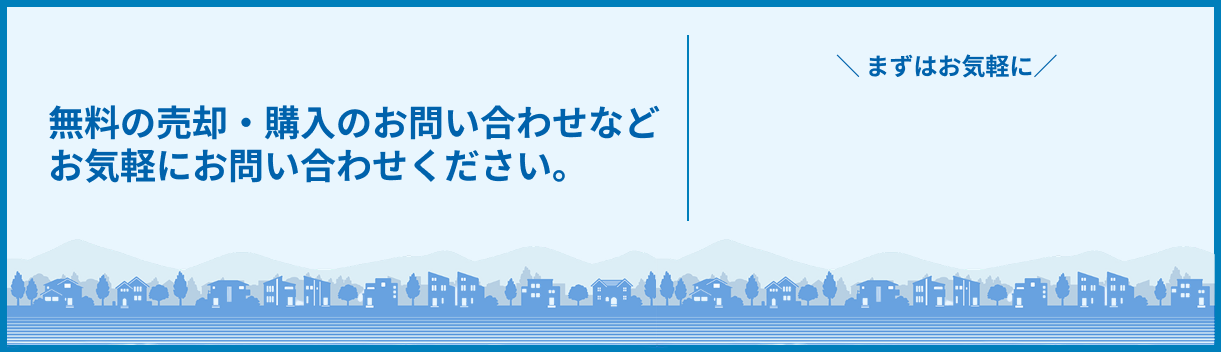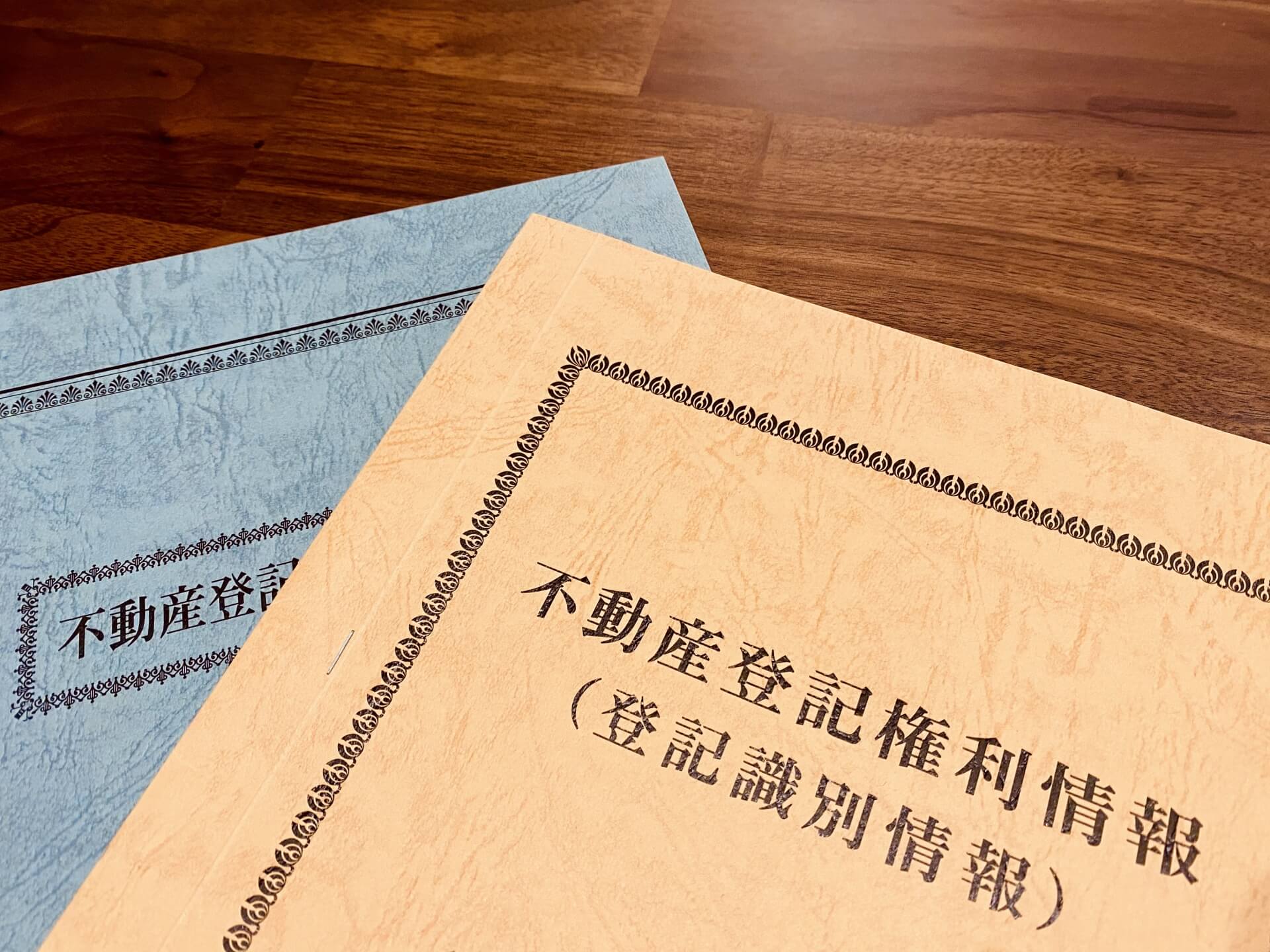そもそも「実家じまい」とは?なぜ今、考えるべきなのか
実家じまいという言葉は知っていても、必要性や効果についてよくわかっていないという人もいるのではないでしょうか。実家じまいの基本的な定義と、現代社会においてなぜ避けて通れない課題となっているのかなどを解説します。
実家じまいの定義:単なる片付けではない、家族の歴史の総仕上げ
「実家じまい」とは、親が亡くなったり、高齢者施設へ入居したりといった理由で誰も住まなくなった実家を整理し、処分または次の世代が活用できる状態にするまでの一連の活動を指します。
単に家の中のモノを片付けること(遺品整理や不用品処分)だけにとどまらず、相続に関する法的な手続きや不動産の名義変更、実家の売却や解体といった不動産の処分まで、多岐にわたる作業の総称が「実家じまい」です。
また、家族が共に過ごした時間や思い出と丁寧に向き合い、その歴史を締めくくるという、非常に精神的な側面も併せ持つ重要なライフイベントと言えます。
なぜ必要?実家じまいをしないと起こる3つのリスク
思い出の詰まった実家をそのままにしておきたい気持ちは、誰にでもあるでしょう。しかし、住む人のいない家を放置することには、多くのリスクが伴います。ここでは、実家じまいをしない場合に起こりうる、代表的な3つのリスクを解説します。
リスク1:【経済的負担】特定空き家に指定され、固定資産税が最大6倍に
管理が行き届いていない空き家は、倒壊の危険性や衛生上の問題、景観を損なうといった理由から、行政によって「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定され、自治体からの改善勧告に従わないと、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。
リスク2:【資産価値の低下】家の老朽化と近隣トラブル
誰も住んでいない家は急速に老朽化が進みます。老朽化に伴い建物の資産価値は下落し、いざ売却しようとしても買い手が見つからないことも多いものです。
さらに、庭の雑草や木の枝が隣の敷地にはみ出したり、害虫や害獣が発生したりすることで、ご近所との思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
リスク3:【家族の負担増】先送りにするほど、時間もお金も余計にかかる
「いつかはやらなければ」と問題を先延ばしにすればするほど、状況は複雑化しがちです。いざという時に慌てて業者を探すと、時間的な制約から不利な条件で契約してしまったり、高額な費用を請求されたりするリスクが高まります。
また、決断を先延ばしにしている間に、自分自身も年を重ね、体力的に片付け作業が困難になる可能性もあるでしょう。早めに行動を起こすことが、結果的に心身と経済的な負担を軽減することにつながります。
実家じまいのタイミングは?「生前」と「死後」の進め方の違い
実家じまいを始めるタイミングは、大きく分けて、親が元気なうちに行う「生前」と、亡くなった後に行う「死後」の2つがあります。
親の生前に行う実家じまい(生前整理)
親の生前に実家じまいを行う最大のメリットは、親の意思を直接確認しながら進められることです。何を残し、何を処分するのか、思い出話を聞きながら一緒に作業することで、親の気持ちを尊重した整理ができます。
また、生前に財産や持ち物を整理しておくことで、将来の相続手続きがスムーズになり、家族間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
なお、最も大切なのは、親の気持ちに寄り添い、決して無理強いしないことです。親にとっては、自分の人生そのものである家や持ち物を手放すことは、大きな喪失感を伴います。「家を追い出される」と感じさせないよう、時間をかけて丁寧にコミュニケーションを取ることが不可欠です。
親の死後に行う実家じまい(遺品整理)
親が亡くなった後に行う場合は、相続人となった兄弟姉妹などで協力し、スケジュールを立てて計画的に進められます。
一方で、相続手続きと並行して進める必要があるため、作業が複雑になりがちです。特に相続放棄(3ヶ月以内)や相続税の申告(10ヶ月以内)など、期限が定められた手続きには要注意です。
また、遺産の分割方法や実家の処分方針を巡って、相続人間で意見が対立し、トラブルに発展する可能性も考慮しておく必要があります。
後悔しない実家じまいの進め方【5つの鉄則ステップ】

実家じまいは、段取りが9割です。場当たり的に進めると、時間も費用も余計にかかってしまいます。ここでは、5つのステップに分けて具体的に解説します。
【ステップ1:最重要】親族会議を開き、方向性を共有する
実家じまいを成功させるための最も重要なステップが「親族会議」です。実家は親だけのものではありません。
この「みんなの家」という認識を共有せず、誰か一人が独断で進めると、後々「聞いていない」「なぜ勝手に決めたんだ」といった感情的なしこりを生み、深刻なトラブルに発展しかねません。
まずは将来的に実家を「売却」するのか、「賃貸」に出すのか、あるいは「誰かが住む」のかについて話し合いましょう。続いて、片付け費用、修繕費、税金など、発生する費用の負担割合を明確にします。全員で均等に割るのか、あるいは実家の相続割合に応じて決めるのか、納得のいくルールを決めておくことが肝心です。
また、実家の近くに住んでいて物理的な作業ができる人、遠方で書類手続きや情報収集を担う人など、それぞれの状況に合わせて役割を決めます。
この話し合いは、できる限り親が元気なうちから始めるのが理想です。親自身の希望を聞けるうえに、家族全員が心の準備をする時間を持てます。
【ステップ2】計画立案と準備|スケジュールと予算を決める
方向性が固まったら、具体的なアクションプランに落とし込みます。まずは、「1年後に売却を完了させる」などの最終的なゴールを設定し、そこから逆算して「いつまでに何をすべきか」を洗い出すとよいでしょう。
また、想定される費用(遺品整理、不動産仲介手数料、税金、解体費用など)をすべてリストアップし、概算の総額を把握します。この時、想定外の出費に備えて、総予算の1〜2割程度の予備費を用意しておきましょう。
この段階で、必要に応じて専門家への相談を開始します。相続手続きなら司法書士、不動産の売却なら不動産業者、片付けが手に負えないなら遺品整理業者など、課題に応じたプロフェッショナルを探し始めましょう。
【ステップ3】実家の片付け|思い出とモノを整理する
実家じまいで最も労力がかかるのが、家財の片付けです。まずは家の中にあるすべてのモノを「残すもの」「売る・譲るもの」「捨てるもの」の3つに分類します。「1年以上使っていないもの」や「同じものが複数あるもの」は処分の候補と考えるなど、自分たちなりのルールを決めると作業がスムーズに進みます。
不動産の権利証、預金通帳、保険証券、有価証券、年金手帳といった重要書類は、後の手続きで必ず必要になります。まとめて一括で保管し、紛失しないよう管理しておきましょう。
仏壇や神棚は単なるモノとして処分できません。お世話になったお寺や神社に連絡し、「魂抜き(閉眼供養)」と呼ばれる儀式を行ってもらうのが一般的です。その後、仏具店や専門の業者に引き取りを依頼しましょう。
【ステップ4】実家の今後を決定し、手続きを進める
片付けの目途が立ったら、ステップ1で話し合った実家の今後について、具体的な手続きを進めていきます。主な選択肢は以下の通りです。
選択肢1:売却する
売却すればまとまった現金が手に入るため、相続人間での遺産分割がスムーズになります。また、固定資産税の支払いや家の管理といった手間からも完全に解放されるでしょう。
一方で、売却すると思い出の詰まった場所が形としてなくなってしまう寂しさがあります。また、物件の状況や市場によっては、売却までに時間がかかるケースもあるでしょう。
選択肢2:賃貸に出す
賃貸に出すメリットは、家賃という形で定期的な収入を得られるうえに、実家を資産として持ち続けられることです。一方で、空室のリスクが常につきまといます。また、設備の修繕費や管理の手間、固定資産税などの維持費がかかり続けるのがデメリットです。
選択肢3:解体して更地にする
実家を解体するメリットは、建物の維持管理が不要になり、倒壊などのリスクがなくなることです。土地として売却しやすくなったり、駐車場として活用したりする道も開けます。
一方で、数百万円単位の解体費用がかかることはデメリットです。また、住宅がなくなることで土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税額が上がってしまう可能性も出てきます。
【ステップ5】各種行政・ライフラインの手続き
不動産の手続きと並行して、生活にまつわる様々な契約の解約や名義変更を進めます。親の死後の場合は、相続人の確定、遺産分割協議、相続登記などが必要です。特に、相続を放棄する「相続放棄」は3ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内と期限が厳しく定められているため要注意です。
また、電気、ガス、水道など契約しているライフラインをすべて解約します。ただし、実家の片付け作業中は電気や水道が必要になるため、解約のタイミングは計画的に決めましょう。
他にも、銀行口座やクレジットカード、保険、各種ウェブサービスの会員登録など、故人名義の契約はすべて解約、または名義変更します。
【いくらかかる?】実家じまいの費用内訳と節約術

実家じまいには、まとまった費用が必要です。しかし、事前に何にいくらかかるのかを把握し、賢く費用を抑える方法を知っておけば、無駄な出費をせずに計画を進められるでしょう。
実家じまいの総額費用は数十万円~1000万円超
実家じまいにかかる費用は、家の広さやモノの量、そして処分方法によってケースバイケースで大きく変動します。主な費用項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- ・遺品整理・不用品処分費用:家の中のモノを片付ける費用
- ・不動産売却に関する費用:仲介手数料や税金など
- ・建物の解体費用:家を取り壊して更地にする場合の費用
- ・各種手続き費用:相続登記などにかかる専門家への報酬
これらはあくまで一例であり、状況に応じてリフォーム費用やハウスクリーニング費用などが加わることもあります。
【費用内訳1】遺品整理・不用品処分費用(10~100万円)
家財の片付けは、実家じまいで多くの人が最初に着手する作業です。その費用は、自分で行うか、専門業者に依頼するかで大きく変わります。
専門の遺品整理業者などに依頼した場合、費用は部屋の間取りや物量に応じて決まるのが一般的です。あくまで目安ですが、1R/1Kで3~8万円、3LDKになると20~60万円程度が相場とされています。大型家具や家電の量、エアコンの取り外しといった付帯作業の有無によっても金額は変動します。
自分でやると費用を抑えられますが、膨大な時間と労力がかかります。主な出費は、自治体の粗大ゴミ処理手数料やゴミ袋代、レンタカー代などです。
費用を抑える最大のポイントは、複数の業者から相見積もりを取ることです。最低でも3社に依頼し、料金だけでなく、サービス内容や対応の丁寧さも比較検討しましょう。
【費用内訳2】不動産売却費用(売却価格の3%~)
実家を売却する場合、売却価格の全額が手元に残るわけではありません。仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料や登記費用などが必要になります。
仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬で、法律で上限が定められています。一般的には「(売却価格×3%+6万円)+消費税」という速算式で計算されることが多く、売却費用の大部分を占めます。
親が住宅ローンを完済していない場合は「抵当権抹消登記」、買主へ所有権を移す「所有権移転登記」などが必要で、これらの手続きを依頼する司法書士への報酬が発生します。費用は数万円から十数万円程度が目安です。
【費用内訳3】解体費用(100~300万円)
解体費用は、建物の構造と広さ(坪数)によって大きく変わります。一般的な目安として、木造住宅で1坪あたり4~5万円、鉄骨造で6~7万円です。30坪の木造住宅であれば、120~150万円程度が相場となります。
見積もり以外に追加費用が発生するケースもあります。例えば、古い建物に使われていることがあるアスベストの除去費用や、庭の木々やブロック塀の撤去費用などです。
【裏ワザ】使える補助金・助成金を活用して費用を抑える
実家じまいにかかる費用負担を軽減するために、国や自治体が設けている補助金・助成金制度があります。
老朽危険家屋解体撤去補助金
倒壊の危険があるなど、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家の解体費用の一部を補助する制度です。多くの自治体で導入されており、数十万円~100万円程度の補助が受けられる場合があります。
相続登記の登録免許税の免税措置
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、手続きにかかる登録免許税が免税となる措置があります。例えば、相続した土地の評価額が100万円以下である場合など、一定の条件を満たせば適用可能です。
【絶対避けるべき】実家じまいの3大トラブルと回避策

実家じまいは順調に進んでいるように見えても、思わぬ落とし穴が潜んでいるものです。多くの人が陥りがちな3つの代表的なトラブルと、それを未然に防ぐための具体的な対策を解説します。
トラブル1:【親族間の対立】「言った・言わない」の泥沼化
実家じまいで最も深刻化しやすく、精神的な負担も大きいのが、家族・親族間のトラブルです。その原因は、「誰が費用をいくら負担するのか」というお金の問題や、「近くに住んでいる自分ばかりが作業している」といった不公平感から生じるケースがほとんどです。
特に、親の思い出の品を巡っては「言った・言わない」の泥沼化を招くこともあります。これを防ぐ回避策が、「親族会議」を開き、話し合った決定事項を議事録として書面に残しておくことです。
また、親が元気なうちに、実家や財産に関する遺言書を作成してもらうことも、相続トラブルを避けるうえで極めて有効な対策となります。
トラブル2:【業者選びの失敗】悪徳業者による高額請求
「業界最安値」といった謳い文句や、極端に安い見積もりを提示してくる業者には要注意です。作業後に「想定外の費用」と称して高額な追加料金を請求されたり、回収した家財を不法投棄されたりするケースが後を絶ちません。
トラブルを避けるためには、必ず3社以上から相見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討しましょう。また、家庭の不用品を回収するには、自治体の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。この許認可の有無を必ず確認してください。
トラブル3:【手続きの遅延】期限を過ぎてペナルティ発生
実家じまいに伴う行政手続きには、厳しい期限が設けられているものが少なくありません。「相続放棄」は特に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、相続税の申告と納税は10ヶ月以内と期限が短く、期限を過ぎると大きな不利益を被る可能性があります。
少しでも「難しい」「自分では手に負えない」と感じる手続きがあれば、迷わず早めに司法書士や税理士といった専門家に相談することが、ペナルティを回避する最も確実な方法です。
実家じまいと向き合うための「心の準備」

実家じまいは、物理的な作業以上に、精神的な負担が大きいものです。自分の心とどう向き合っていくべきか、後悔しないためのヒントをお伝えします。
気持ちの整理:焦らず、自分のペースで進める
思い出の品を前にして、作業の手が止まってしまうのは自然のことです。無理に1日で終わらせようとせず、「今日はこの引き出しだけ」など、小さなゴールを設定しましょう。
「捨てる」ことへの罪悪感ではなく、「ありがとう」という感謝の気持ちで手放すことが、心を軽くする第一歩です。
家族との協力:一人で抱え込まず、弱音を吐く
実家じまいの大変さを感じているのは、あなただけではありません。兄弟姉妹や親族と「疲れたね」「大変だね」と弱音を吐き合うだけでも、気持ちは楽になります。作業の進捗だけでなく、お互いの気持ちをこまめに共有し、チームで乗り越えていきましょう。
専門家を頼る:心の負担も軽くしてくれる味方
遺品整理士や各種専門家は、作業を代行してくれるだけでなく、依頼者の心に寄り添うプロでもあります。何から手をつけていいか途方に暮れた時こそ、専門家に相談することで進むべき道筋が見え、心の負担も軽くなります。
自分自身を労わる:未来のための「卒業式」と捉える
実家じまいは、過去との悲しい決別ではありません。たくさんの思い出に感謝を込めて送り出す、家族にとっての「卒業式」です。未来への一歩と前向きに捉えることが、後悔しないための最大のコツです。
実家じまいの「よくある質問」Q&A
ここからは、実家じまいについて寄せられることの多い疑問に答えていきます。
Q1. 遠方に住んでいて、なかなか実家に行けません。どうすればいいですか?
遺品整理から不動産売却まで、ワンストップで代行してくれる専門業者もいます。帰省した際に親族会議と現地調査を行い、信頼できる業者を見つけて任せるのが現実的です。
Q2. 仏壇や神棚はどうすればいいですか?
菩提寺や神社に相談し、「魂抜き」「お焚き上げ」などの供養をしてもらいます。その後、仏壇・仏具店や専門の処分業者に引き取ってもらうのが一般的です。
Q3. ご近所への挨拶は必要ですか?
必要です。解体工事を行う場合は特に、騒音やホコリで近隣に迷惑をかけるため、事前に作業内容や期間を伝えて挨拶に回りましょう。売却や片付けで人の出入りが多くなる場合も、一言伝えておくとスムーズです。
実家の売却を進めていきたい人はグラングッド不動産へご相談ください
実家の売却を検討しているなら、グラングッド不動産にご相談ください。グラングッド不動産は、福岡で地域密着型の強みを持つほか、丁寧で親身な対応をご評価いただいています。「何から始めたらよいかわからない」「売却後の手続きが不安」といった初めての方でも安心してご相談いただけます。
当社では、住宅ローンや税金、火災保険など、売却後のライフプランまで見据えたサポートを得意としており、お客様一人ひとりの状況に応じた資金計画やアドバイスを提案しています。相続や資産整理、住み替えなど、複雑な背景を伴う売却にも柔軟に対応可能です。
さらに、購入・売却後のアフターサポートにも力を入れており、不動産取得税や固定資産税の手続き、近隣トラブルの対応、さらには将来の相続・贈与・資産売却まで、生涯にわたる相談相手としてご対応します。
「相談したらすぐに契約を迫られるのでは…」という不安を感じている方にも、押し売りのないスタンスで、気軽に話せるパートナーとして信頼されています。福岡エリアで納得のいく不動産売却を目指すなら、ぜひグラングッド不動産を相談先の一つとしてご検討ください。
まとめ
実家じまいは、単なる片付けではなく、法的手続きや費用の問題、そして家族の歴史と向き合う、心身ともに大きな負担を伴う一大プロジェクトです。問題を先送りにすると、固定資産税の増額や資産価値の下落といった、さらに大きなリスクにつながる可能性があります。
実家じまいを成功させる鍵は、「事前の準備」と「家族間の情報共有」に尽きます。親が元気なうちから親族で話し合いの場を持ち、計画的にステップを踏むことで、トラブルを未然に防ぎ、費用を抑えることも可能です。