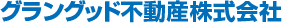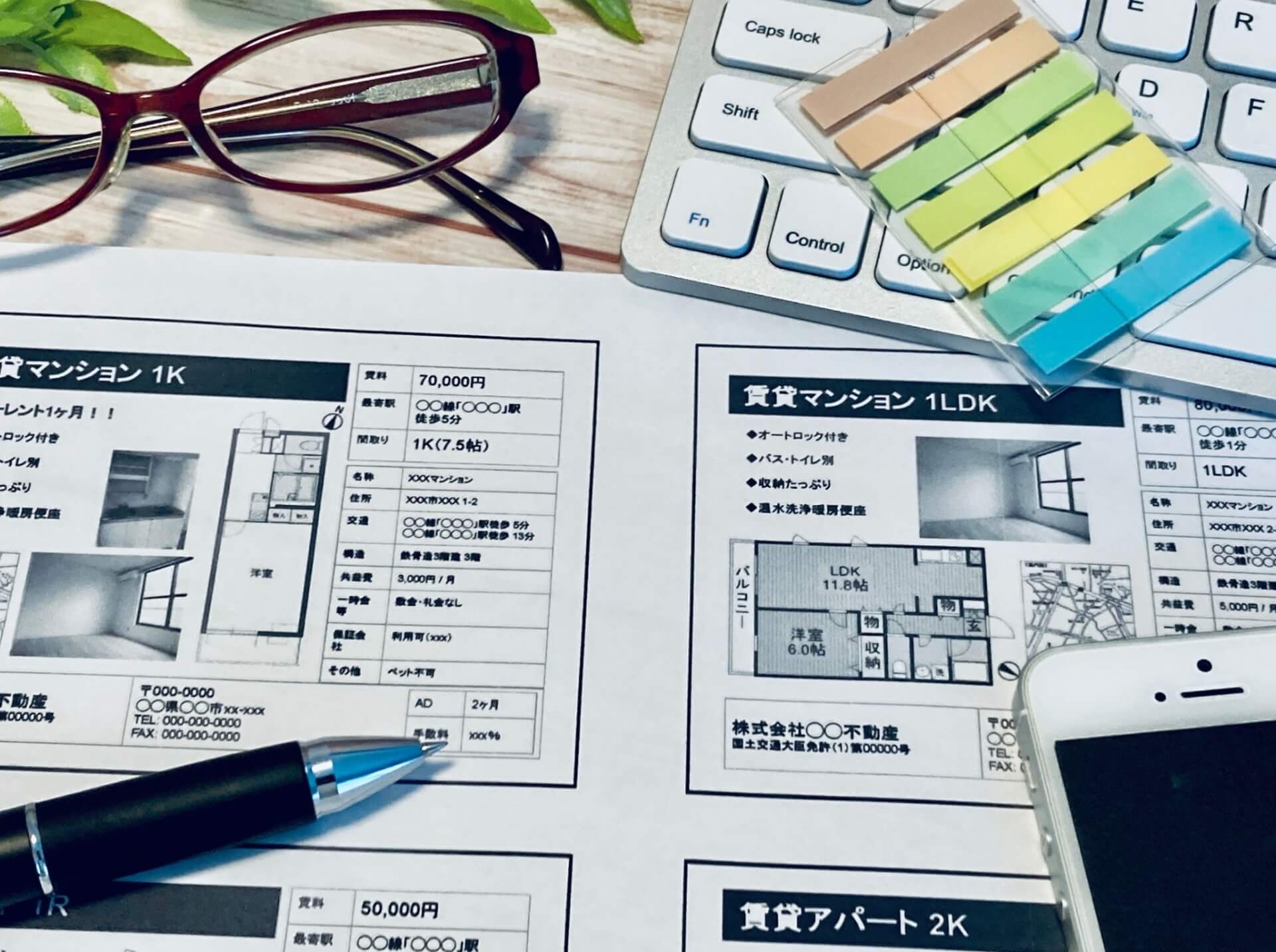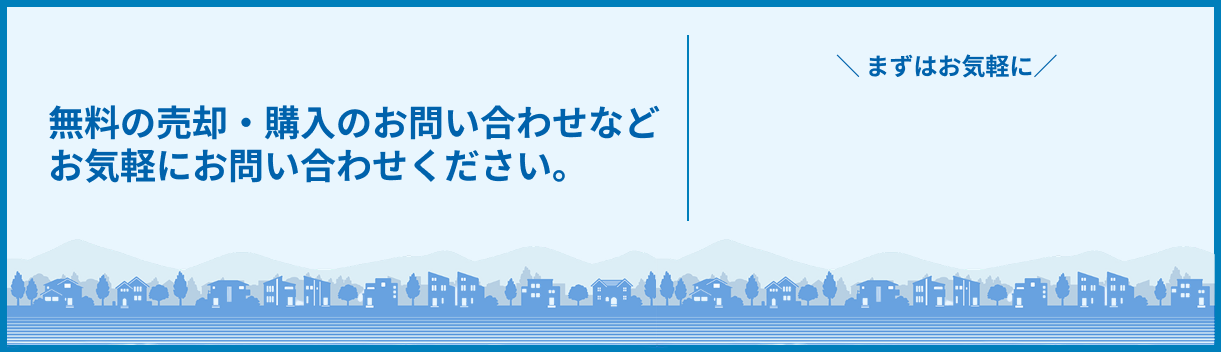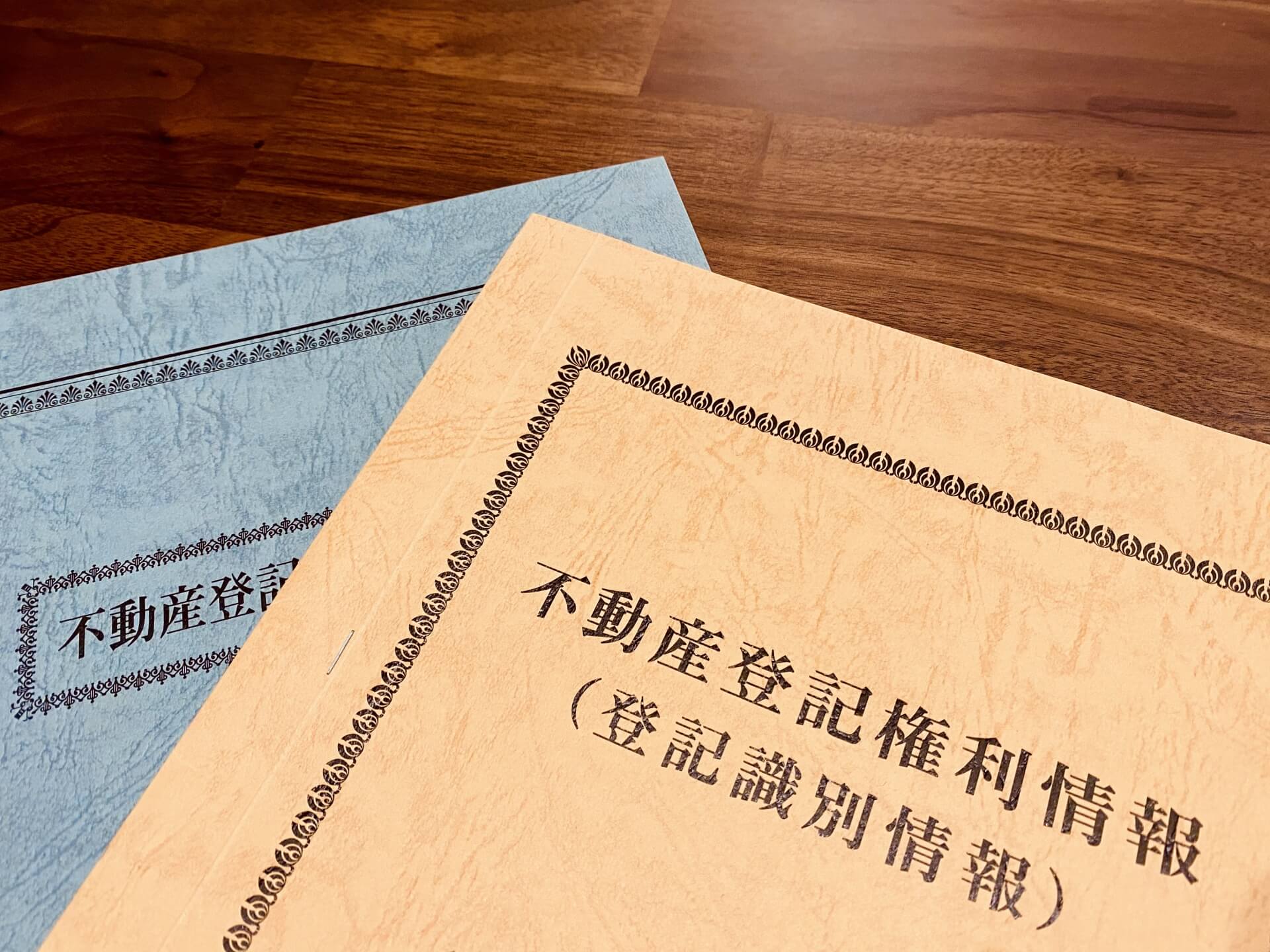まずは整理!不動産売却チラシの3つのタイプと特徴
ポストに投函される不動産関連のチラシには、目的やターゲットによって複数のタイプがあります。一見似ているように見えても、実はまったく異なる意図で配布されていることも多いものです。
まずは「売主向け」「買主向け」「買取型」など、代表的なチラシの種類とそれぞれの特徴を整理して理解しておきましょう。
売主向けと買主向けの違いとは?
不動産チラシは大きく「売主向け」と「買主向け」の2つに分けられます。「売主向けチラシ」には、「この地域で物件を探しているお客様がいます」「無料査定実施中」などと記載されています。不動産会社がチラシを配る目的は売却依頼の獲得です。
一方で、「買主向けチラシ」は、既に売却依頼を受けた物件の情報を掲載し、購入希望者を募るための広告です。「○○駅徒歩○分」「○○万円」など、具体的な物件情報が記載されており、ポスティングや新聞折込などを通じて広く配布されます。
売主向けか買主向けかを見分けるポイントは、「物件が紹介されているかどうか」「売却依頼を促す文言があるか」です。売主向けチラシには、必ずしも信頼性の高い情報が記載されているとは限らないため、内容を慎重に見極めることが重要です。
「買取型」か「仲介型」かも見極めよう
売主向けのチラシの中には、「当社が直接買い取ります」「即日現金化可能」などと書かれているものもあります。これは「買取型」のチラシであり、不動産会社が自社で物件を買い取り、リフォーム後に再販売を行うことを目的としています。
その一方で、「仲介型」のチラシは、売主と買主の間に不動産会社が入って売買契約を成立させるスタイルで、一般的な不動産売却の手段です。こちらのチラシには「仲介手数料無料」「高額査定」などの表現が使われることもあります。
売主にとっては、不動産の買取には早く現金化できるメリットがあります。ただし、相場より2~3割低い価格での売却になるケースもあるため要注意です。仲介型は市場価格に近い金額で売れる可能性がありますが、売却完了までに時間がかかることもあります。
チラシの文言をよく読み取り、自分が希望する売却方法と合っているかを判断することが大切です。購入希望者の存在をアピールしていても、それが「仲介」なのか「買取」なのかで、対応や売却価格が大きく変わってくるため注意しましょう。
「高く買います」は信じていい?よくあるチラシ文言のウラ側

不動産売却のチラシには、思わず期待してしまうような言葉が並んでいることも少なくありません。
「高額査定」「今がチャンス」「すぐに買い手がいます」といった文言は、一見魅力的に見えますが、その裏にある意図やリスクを知らないまま連絡してしまうと、思わぬ損をすることもあるでしょう。
「購入希望者がいます」は定番だが信頼できる?
「当マンションを○○万円で購入希望のお客様がいます」という文言は、売主向けのチラシで最もよく見かける定番表現の一つです。不動産会社が実際に購入検討者を抱えている場合もありますが、そのほとんどは「物件を売らせるための営業トーク」と考えておくべきです。
実際のところ、本当に見込み客がいるかはわかりません。買主の存在をにおわせる表現は、あくまでも売主に連絡を促すためのフックとして使われているケースが多いものです。
特に「当地区限定」「複数名が検討中」といった文言は、複数の地域やマンションで一斉に配られている汎用的なチラシである可能性が高いです。
本当に購入希望者が存在するかを確かめたい場合は、「その方の希望条件や希望価格を具体的に教えてください」と問い合わせてみましょう。明確な回答が得られない場合は要注意です。
「期間限定査定」や「即日買取」は急かす手口?
「○月○日までの期間限定」「即日現金買取可能」といった文言も、売主の関心を引くためによく使われる表現です。不動産の査定価格や売却価格は、多少の変化はあれども、売却時期によってそれほど大きく変動するものではありません。
こうした表現は、売却の意思決定を急がせることで、冷静な判断をさせないようにする「心理的誘導」とも言えます。
また、「即日買取可能」と書かれている場合は、「仲介」ではなく「買取型」のチラシである可能性が高く、相場より安く買い取られるリスクもあります。「早く売れる」と「高く売れる」は同じではないという点に要注意です。
急いで売りたい場合でも、こうした表現に飛びつくのではなく、複数の不動産会社に査定依頼をして相場感を持つことが大切です。
そのチラシ、どこであなたを知った?情報取得の仕組みと対処法

投函されたチラシを見て「なぜ自分の家にチラシが届いたのか?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。不動産会社があなたの所有する物件や氏名を知っている背景には、法的に取得可能な情報ソースが存在します。
登記簿謄本・法務局・相続情報などの取得ルート
不動産会社が所有者の情報を知る方法の一つは、登記簿謄本です。法務局で取得できる登記簿には、土地や建物の所在地だけでなく、所有者の氏名や住所が明記されており、誰でも取得できます。
登記簿謄本を取得することにより、不動産会社は特定の物件の所有者に向けてチラシやダイレクトメール(DM)を送れます。
また、相続登記が完了した直後には、相続情報を元に営業をかけるケースもあります。登記情報を活用した名簿を販売する業者も存在し、不動産会社がその情報を利用して相続不動産の売却提案を行うこともめずらしくありません。
登記簿謄本や相続情報と聞くと、個人情報の流出のように感じられるかもしれませんが、登記情報は公的なものとして一般公開されているものです。不動産業界では、「物上げ営業(物件仕入れのための営業活動)」のために広く活用されています。
知らない業者からのDMが不安なときの対応策
突然届くチラシやDMに不信感を抱くのは自然なことです。特に、見たこともない不動産会社からの案内に「なぜ自分宛てなのか」「信頼できるのか」と不安になる方もいるでしょう。こうした不安を感じた場合は、以下のような対応策を取るのがおすすめです。
まず、チラシに記載されている会社名や免許番号をインターネットで検索してみてください。宅建業免許番号が記載されていない、電話番号が携帯のみ、住所がない、などの場合は要注意です。また、Googleマップや口コミサイトでの評価も参考になります。
さらに、内容に具体性がないチラシや「急いでご連絡を」など不安を煽る文言が含まれているものは、無理に対応せず無視して構いません。不安が大きい場合は、消費生活センターや宅建協会などに相談するのも一つの方法です。
チラシの不動産会社を見極める5つのチェックリスト
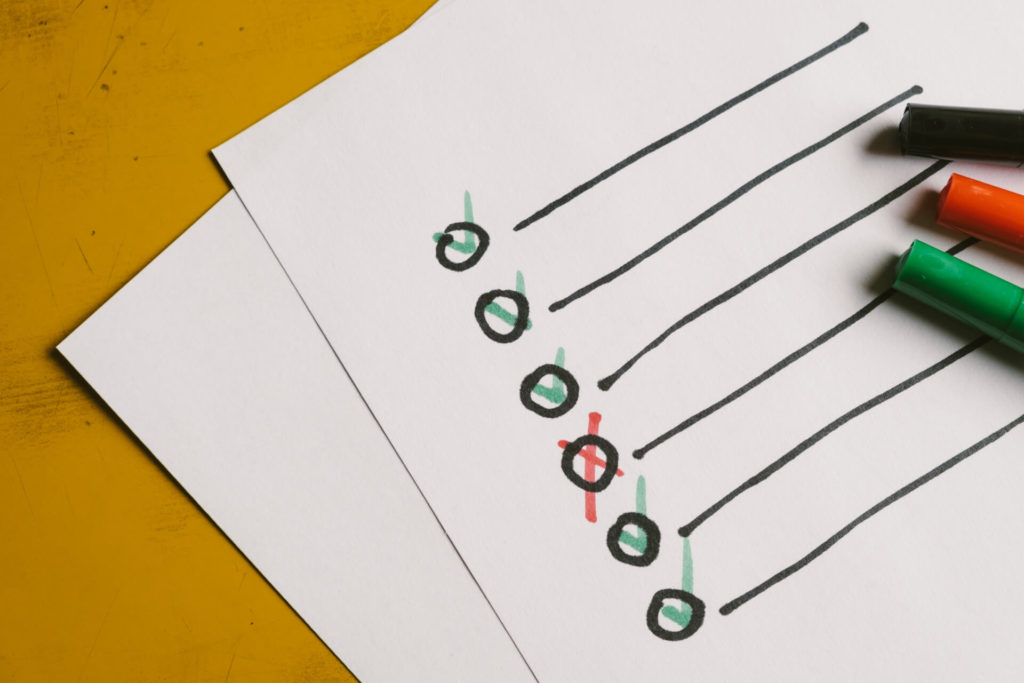
チラシを見て不動産の売却に興味を持ったとしても、記載されている不動産会社が本当に信頼できるかどうかは、慎重に見極める必要があります。トラブルを避けるためには、いくつかの確認ポイントを把握しておくことが重要です。
ここでは、チラシを投函してきた不動産会社に売却を任せても良いのか、判断するための実践的なチェック項目を紹介します。
宅建業免許番号と所在地が明記されているか?
まず注目すべきポイントの一つ目は、「宅地建物取引業免許番号(宅建業免許番号)」がチラシに記載されているかどうかです。これは不動産会社が合法に営業するために必要な許可であり、国土交通省の「宅地建物取引業者検索システム」でも確認できます。
加えて、会社の所在地や固定電話番号の記載があるかも重要なポイントです。所在地が不明瞭だったり、連絡先として携帯電話の番号しか書いていなかったりといった場合は、実体のない会社や悪質な業者である可能性もあります。信頼性の高い不動産会社であれば、こうした情報を必ず明記しているものです。
「内容が具体的か」「言葉に誇張がないか」を見る
チラシに記載された内容があまりに曖昧だったり、「今なら○○万円で売れます!」「お急ぎください!」などの誇張表現が目立ったりといった場合は要注意です。具体的な購入希望者の条件や購入価格などが明記されているかをチェックしましょう。
例えば、「当エリア限定で探している方がいます」と書かれているだけでは、その裏付けを取ることは困難です。信頼できる会社は、チラシの表現に根拠を持っており、読者に誤解を与えるような文言を避ける傾向があります。
「絶対」「確実」「最高値」など、「過度に断定的な表現や法的に禁止された用語(誇大広告)」が使われていないかといった点も要チェックです。
ネットでの評判・過去実績も確認する
気になる不動産会社があるなら、インターネットで会社名を検索し、評判や口コミを確認することも大切です。Googleのビジネスプロフィール、不動産ポータルサイトのレビュー、SNSでの口コミなどから、実際に利用した人の評価を確認できます。
また、公式サイトがある場合は、過去の売却実績や取り扱い物件数、地元での営業年数などもチェックポイントです。特に地域密着型の会社は、エリア特化の強みや丁寧なサポート体制をアピールしていることが多く、これらの情報は信頼に値する材料となるでしょう。
ネット上の情報を鵜呑みにする必要はありませんが、実績と評判を併せて見ることで、不動産会社の信頼性を客観的に判断する一助になります。チラシだけではわからない情報もオンラインでは調べられるため、有効に活用しましょう。
査定額は高ければいい?「あとで後悔しない」価格の考え方

不動産売却のチラシに「高額査定」「他社より高く買います」などと書かれていると、つい期待してしまうものです。しかし、査定額が高いからといって、それがそのまま売却価格になるとは限りません。
ここでは、査定額と実際の売却額の違いや相場を無視した価格設定によるリスクについて解説していきます。
「査定額=売却額」ではない理由
不動産の「査定額」とは、あくまで不動産会社が提示する見積価格であり、実際にその価格で売れることを保証するものではありません。
査定には、周辺相場、過去の成約事例、築年数、面積、リフォーム履歴などの要素が反映されますが、最終的な売却価格は「買主が納得して購入する金額」です。
そのため、複数の不動産会社に査定を依頼すると、査定額に数十万〜数百万円の差が出ることも少なくありません。この差は、各社の販売戦略や営業方針による部分が大きく、査定額が高い=信頼できる会社とは限らない点に要注意です。
査定額は、売主にとっての参考指標であり、買主の動向や市場の需給バランスによって上下する可能性があるという前提で捉えるようにしましょう。
相場より高い査定にはこんな落とし穴がある
「他社より高く査定します」と記載されたチラシには要注意です。不動産会社によっては、媒介契約を取りたいがために、あえて相場より高い査定額を提示することがあります。
売主が査定額に期待して専任媒介契約を結んだ後、しばらくして「なかなか反響がないので価格を下げましょう」と言われるパターンはめずらしくありません。
このような価格戦略は「高値掴み」と呼ばれ、売却期間が長引く原因となります。売却期間が長引くほど、買主からは「この物件は何か事情があるのでは」と警戒され、かえって敬遠されてしまうことも少なくありません。
「最初から相場に合わせて売り出していれば、もっと早く、好条件で売れたかもしれない」となってしまうリスクがあります。
高い査定額が出た場合は、「なぜその価格なのか」「過去の成約事例と比較して妥当か」を問い合わせ、根拠のある妥当な査定なのかどうかを見極めることが大切です。
安全に売却するなら?比較すべき選択肢とその使い方

不動産売却を検討する際、「チラシの業者に連絡するか」「ネットの一括査定サイトを使うか」「地元の不動産会社に相談するか」など、複数の選択肢があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自分に合った方法を選ぶことが、納得のいく売却とトラブル回避につながります。代表的な選択肢の違いと活用法を解説します。
一括査定サイトとチラシ業者、どう使い分ける?
不動産売却の情報収集手段として代表的なのが「チラシ」と「一括査定サイト」です。それぞれ性質が異なるため、使い分け方を理解しておきましょう。
一括査定サイトは、インターネット上で複数の不動産会社へ一度に査定を依頼できる仕組みで、売却価格の相場感をつかむためには非常に便利です。
査定額や担当者の対応を比較できるため、信頼できる会社を見極めやすいのが最大のメリットです。全国展開している大手業者から地域密着型の業者まで、幅広く選べます。
一方で、チラシを送ってくる業者は、特定エリアの物件に特化しているケースが多いものです。ポスティングや法務局の登記簿情報を元にした営業は「物上げ」が目的であり、実際に買い手がいるとは限りません。
そのため、まずは一括査定サイトを使って複数の不動産会社から査定を取得し、チラシ業者の提示内容と照らし合わせて判断するのがおすすめです。情報の裏付けを取るための手段として、双方をうまく活用しましょう。
地元密着型の業者ならではの強みとは?
例えば福岡のように地域性が強く、不動産市場の特徴がエリアごとに細かく違っているエリアでは、地元密着型の不動産会社に相談するメリットはとても大きいと言えます。
地元密着型の不動産会社はエリアの相場感に精通しており、過去の取引事例や売却時期ごとの動向を把握しているため、的確な価格設定と販売戦略を提案してくれます。
さらに、一帯の地主ネットワークや独自の顧客リストを保有している場合もあり、レインズや不動産ポータルサイトなどに頼らずとも売却できるケースもあります。
地元密着型の会社を選ぶ際は、「そのエリアでの販売実績が豊富か」「営業担当が誠実な対応をしているか」「説明が丁寧か」といった視点で比較することが重要です。
チラシで届いた業者が地元密着型であれば、一度面談して判断するのも良いでしょう。地元の事情を知るプロだからこそ、安心して任せられる売却パートナーになる可能性があります。
不安を安心に変える!売却前にやっておきたい3つの準備

不動産の売却は、人生でも数少ない大きな取引です。そのため、どのタイミングで、どの業者に依頼し、どのように進めていくかを事前に整理しておくことが、安心して売却を進めるためのカギとなります。ここからは、売却前にやっておくと後悔しにくくなる3つの基本的な準備について紹介します。
相場のリサーチは自分でもできる
不動産の売却価格を考えるうえで、「相場を知ること」は最も基本的かつ重要なステップです。入ってきたチラシに記載されている金額が妥当かどうかを判断するためにも、自分なりにエリアの相場を把握しておくことが大切です。
具体的には、不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホーム、HOME'Sなど)で、同じエリア・築年数・間取り・面積の物件を検索すれば、ある程度の売り出し価格帯が見えてきます。
また、併せて国土交通省が公開している「不動産取引価格情報検索サイト」も見ておくと安心です。こちらのサイトでは、実際の成約事例を確認できます。
「ポータルサイト」と「成約事例」の2段階でリサーチをしておけば、不動産会社から提示される査定額に対して、「なぜこの価格なのか?」と具体的に質問できるでしょう。
家族や信頼できる第三者に相談する
不動産の売却は、今後の住まいやライフプランにも影響を及ぼします。そのため、一人で決断せず、家族や信頼できる第三者と相談しながら進めることが重要です。
特に、相続した不動産や実家の売却など、感情的な葛藤があるケースでは、第三者の視点を交えることで冷静な判断がしやすくなります。また、家族と方針が共有できていないまま進めると、売却後に「こんなはずではなかった」というトラブルになることもあるでしょう。
可能であれば、不動産に詳しい知人やFP(ファイナンシャルプランナー)などの中立的な立場の人にも相談し、複数の意見を取り入れることで、売却の意思決定に自信が持てるようになります。
福岡での不動産売却ならグラングッド不動産へ
福岡県内で不動産の売却を検討しているなら、グラングッド不動産にご相談ください。グラングッド不動産は、福岡で地域密着型の強みを持つほか、丁寧で親身な対応をご評価いただいています。「何から始めたら良いかわからない」「売却後の手続きが不安」といった初めての方でも安心してご相談いただけます。
当社では、住宅ローンや税金、火災保険など、売却後のライフプランまで見据えたサポートを得意としており、お客様一人ひとりの状況に応じた資金計画やアドバイスを提案しています。相続や資産整理、住み替えなど、複雑な背景を伴う売却にも柔軟に対応可能です。
さらに、購入・売却後のアフターサポートにも力を入れており、不動産取得税や固定資産税の手続き、近隣トラブルの対応、さらには将来の相続・贈与・資産売却まで、生涯にわたる相談相手としてご対応します。
「相談したらすぐに契約を迫られるのでは…」という不安を感じている方にも、押し売りのないスタンスで、気軽に話せるパートナーとして信頼されています。福岡エリアで納得のいく不動産売却を目指すなら、ぜひグラングッド不動産を相談先の一つとしてご検討ください。
まとめ
不動産売却のチラシには有益な情報もありますが、全てのチラシが信用できるというわけではありません。不動産会社選びで失敗しないためには、誇大表現や根拠のない高額査定に惑わされない冷静な判断が必要です。
また、不動産価格の相場を把握したり、信頼できる第三者へ相談したりといった、事前の準備を丁寧に行うことが納得のいく売却への第一歩です。