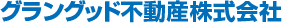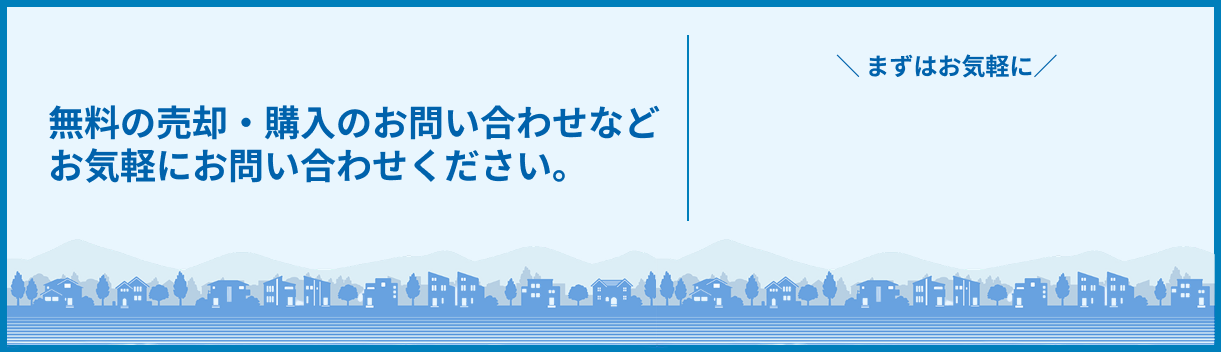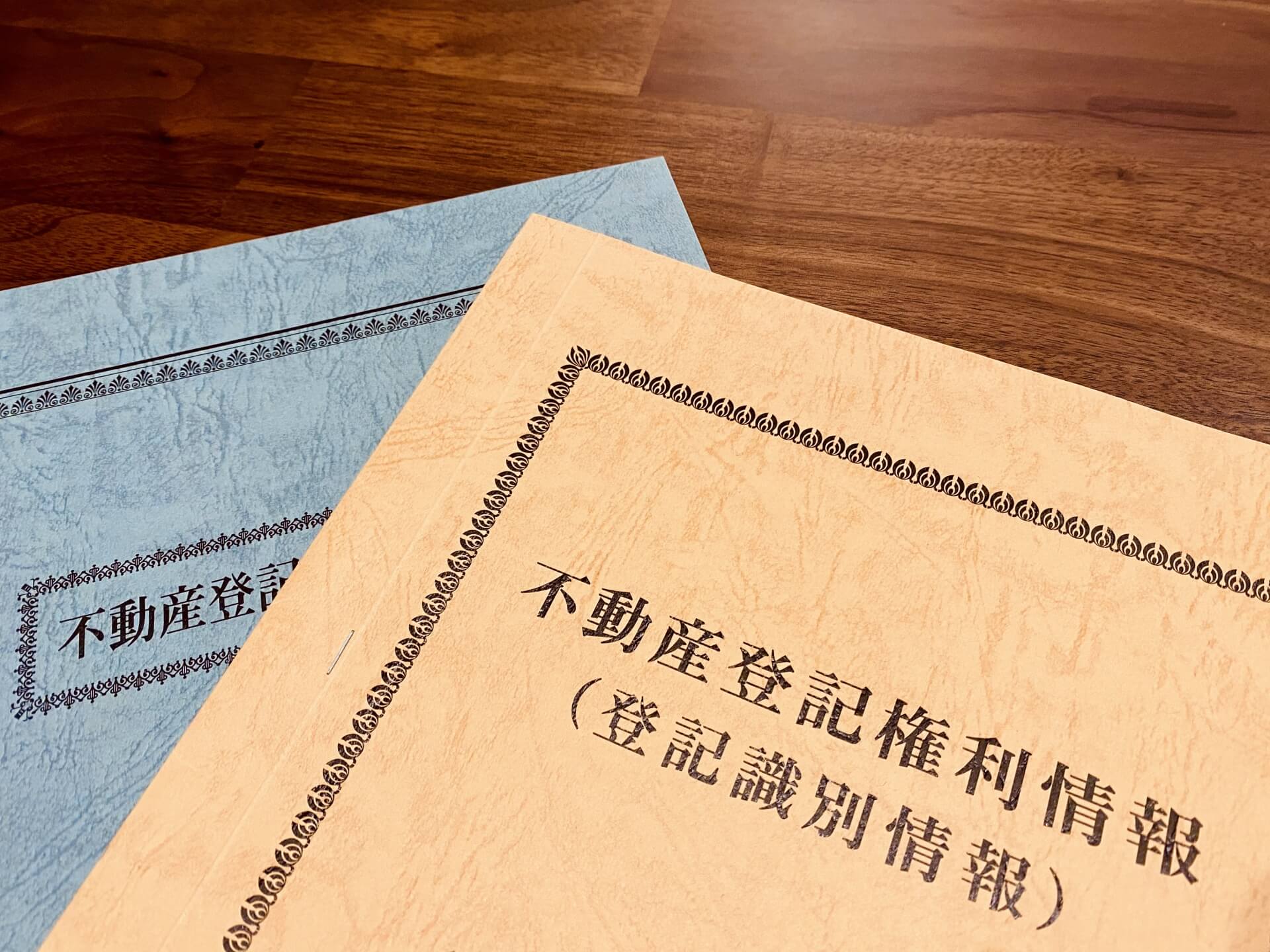今、認知症の親の不動産を売りたい…まず知っておくべき現実
親が認知症を患い、施設へ入所することになった、あるいは自宅への帰宅が見込めなくなったとき、空き家となる実家の処分について悩む方は少なくありません。
固定資産税の負担や建物の老朽化、空き家になったときのリスクなどを考えれば、できるだけ早く売りたいと考えるのは自然なことです。しかし、認知症の進行度などによっては、思うように手続きを進められない可能性もあります。
まずは、「本人に売却意思があると認められるかどうか」という視点から、不動産売却の可否がどのように判断されるのかを見ていきましょう。
意思能力がなければ契約は無効に
不動産の売買契約は、契約内容を理解し、自分の意思で契約に合意できる「意思能力」がなければ成立しません。意思能力とは、法律行為の結果を自分で判断できる力のことです。認知症が進行している場合には、この能力が欠けていると判断されることがあります。
たとえ契約書に本人の署名や押印があっても、契約の時点で意思能力が認められなければ、契約自体が無効とされる可能性もあるため要注意です。
意思能力がグレーな状態ではどう判断される?
一方で、認知症と言っても、その進行度や症状の現れ方は人それぞれです。会話ができる、日常生活にある程度支障がないといった場合でも、契約に必要な意思能力があるとは限りません。
そのため、買い主または売り主に認知症の疑いがある場合は、売買契約の締結や決済に際して司法書士や不動産会社の担当者が本人と面談し、意思能力の有無を確認します。本人が自分の住所・氏名を言えるか、不動産売買の意味を理解しているかといった点がチェックされ、疑わしい場合は医師の診断書が求められることもあります。
認知症の家族に代わって売却はできる?

認知症の親の代わりに子どもが不動産を売却したいと考えるケースは少なくありません。特に親が寝たきりで外出できない、会話が難しいといった状況では「家族が手続きを代行できないだろうか」と考えるのは自然なことです。
しかし、不動産の売買は高額な取引であり、法律的にもさまざまなルールが定められています。たとえ家族であっても、勝手に契約を結ぶことは原則として認められていません。ここからは、委任状による代理売却の可否や注意すべき事例などについて解説します。
委任状での売却は原則NG
「親が売却の意思を示しているから、委任状をもらえば自分でも売却できるだろう」と考える方は多いのではないでしょうか。しかし、認知症の症状が進んでいて親の判断能力が不十分な場合は、たとえ委任状があってもその法的効力を認められない可能性があります。
委任状とは、本人が自分の意思で第三者に権限を委ねる文書です。つまり、本人が「権限を委ねる意思能力」を持っていることが前提としたもので、本人が自分の意思で委任状を書いたと証明できなければ効力がありません。
このため、親がすでに認知症を発症していたタイミングで作成された委任状は、無効と判断されることがあります。不動産売買においては特に、司法書士や金融機関などが厳格に本人確認を行うため、委任状のみで手続きを進めるのは得策ではありません。
こんなケースでも売却は違法になる可能性がある
相続不動産などの売買においては「親が話せなくなってから売却を進めた」「兄が勝手に売却していた」「家族の了承は得ているから大丈夫」といった事例が多いものです。しかし、これらの事例では後に親族や第三者から契約の無効を主張されて、トラブルに発展する可能性があります。
例えば、親が認知症を発症した後に長男が「介護費用のため」として実家を売却した場合でも、法的な手続きを踏まずに行った契約は無効とされる可能性があるため要注意です。また、共有名義の不動産を一部の相続人が単独で売却する行為も違法とみなされる可能性があります。
リスク対策として、本人の判断能力が明確であるうちに制度的な対策を講じるか、すでに判断能力を失っている場合は、成年後見制度などの法的手段を通じて進めることが重要です。安易に「家族だからできる」と考えず、必ず専門家に相談してから行動するようにしましょう。
成年後見制度とは?制度の全体像と使い方

ここまで解説してきたように、認知症の親が自分の意思で不動産売却をできない場合、法律的に正当な手続きを踏まないと売却することはできません。そこで活用されるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度の仕組みと役割
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった高齢者などを法的に支援する仕組みです。財産管理や契約の代理を行う「後見人」を家庭裁判所が選任することで、本人の権利を守りつつ、必要な法律行為を代行できるようにします。
本人が不利益を被らないよう、売買契約や金銭管理などを後見人が代理で行うことにより、安全かつ公正な形で本人の生活や財産を維持していくことを目的とするものです。成年後見制度には大きく分けて以下の2種類があります。
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している場合に利用する
- 任意後見制度:将来に備えて判断能力があるうちに契約しておく
認知症がすでに進行しているケースでは、基本的に法定後見制度が使われます。家庭裁判所から選任されることで、後見人の判断による不動産の売却や契約締結などが可能です。一方で、後見人には「本人の利益を守ること」が求められるため、勝手な不動産の売却やその他資産の処分などは認められません。
後見人になるにはどうすればいい?
成年後見人は家庭裁判所への申し立てによって選任されます。申し立てを行えるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族・市町村長などに限られており、申立先は本人が住民登録している住所地を管轄する家庭裁判所です。
申し立ての際には、以下のような書類や費用が必要になります。
- 本人や親族の戸籍謄本・住民票
- 医師による診断書(判断能力の有無を判断)
- 申立書・財産目録・収支予定表など
- 手数料・郵便切手・登記費用など(合計で1万〜1万5,000円程度)
家庭裁判所は、申し立ての内容や本人の状況を審理したうえで、適任と判断した人物を後見人に選任します。なお、親族だけではなく、弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選ばれることもあります。近年では、親族による不適切な財産管理を防ぐ目的から、第三者が後見人として選ばれるケースもめずらしくありません。
後見制度で不動産を売るための具体的ステップ
後見制度を利用して認知症の親が所有する不動産を売却するには、以下の手順を踏む必要があります。
①成年後見制度の申し立てを行う
まず、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に対し、成年後見開始の申し立てを行います。申し立てから審判までにかかる時間は通常1〜2か月程度です。
②家庭裁判所による後見人の選任
審判が確定すると、家庭裁判所から後見人が選任され、後見登記が行われます。この段階で初めて、後見人は法的に代理権を持つことになります。
③不動産の査定・媒介契約の締結
売却予定の不動産について不動産会社に査定を依頼し、査定内容に納得した段階で後見人が媒介契約を結びます。
④家庭裁判所から売却許可を得る(居住用の場合)
本人が住んでいた自宅など、生活の本拠となる居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りるまでに数週間から1か月程度かかることがあります。
⑤買い主との契約締結・引き渡し
売却価格やその他条件について買い主と合意できたら、売買契約を締結し、決済・引き渡しを行います。契約書には後見人が署名押印し、必要書類を整えて手続きを完了させます。
後見制度を使って不動産を売却するには一定の手間と時間がかかりますが、正しい手順を踏めば、家族が合法的に資産を処分可能です。
制度を使わずに売りたい人のための現実的な代替案
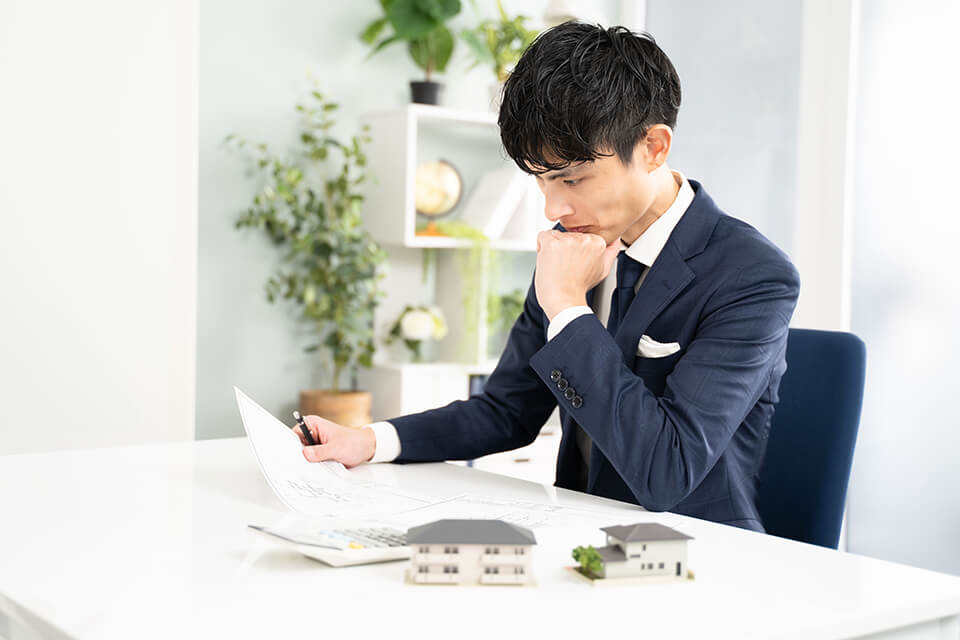
成年後見制度は、認知症の親の財産管理や不動産売却を法的に進めるうえで有効な手段です。しかし「費用がかかる」「時間がかかる」「自由に資産を動かせない」などの理由により、できれば使いたくないと考える方も少なくありません。
そこで注目されているのが、親がまだ元気なうちに準備できる代替手段です。成年後見制度を使わずに将来の不動産売却をスムーズに進めるための選択肢として、「家族信託」と「生前贈与・名義変更」の2つの方法を紹介します。
家族信託の活用:親が元気なうちに備える方法
家族信託とは、本人(親)が判断能力を持っているうちに、特定の財産を信頼できる家族(子どもなど)に託し、その財産を将来にわたって管理・処分してもらう仕組みです。
不動産を信託財産として契約に組み込んでおけば、親が認知症を発症した後でも、受託者による資産の売却や運用が可能になります。
家族信託の大きなメリットは、「成年後見制度と異なり、柔軟かつ自由度の高い財産管理をできる点」です。信託契約には、「売却の条件」や「使途の制限」などを細かく盛り込めるため、親の意思を尊重しながら資産を活用できます。
ただし、家族信託を利用するには、本人が判断能力を持っている必要があります。すでに認知症が進行している場合には利用できません。また、契約書の作成に当たっては、信託に詳しい司法書士や弁護士などへ相談することをおすすめします。
生前贈与や名義変更でリスクを回避できるか?
「親名義の家を売るのが難しいなら、いっそ元気なうちに名義を子どもに変えておけば良いのでは?」という考えから、生前贈与や名義変更を検討する方もいます。しかし、この方法にはいくつかの注意点があります。
まず、贈与には税金がかかる点に要注意です。年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されるため、土地や建物などの不動産を贈与すると、評価額によっては高額な税負担になることもあります。また、名義変更後に「親の意志に反して名義を奪われた」と他の相続人が主張した場合、相続トラブルの火種になるリスクもあるでしょう。
さらに、生前に不動産を贈与した後も親が住み続ける場合は、「不動産を譲ったのに、使用権が残っている」などの複雑な問題も発生しやすくなります。
生前贈与や名義変更は、シンプルなように思えますが、税金・相続・親族間の信頼関係など、複数のリスクが絡むため、事前に専門家と相談しながら慎重に判断することが必要です。
売却を急ぐ人が陥りやすい3つの落とし穴

「介護施設の入所費用が今すぐ必要」「空き家の管理や税金負担が限界」といった理由から、認知症の親の不動産売却を急ぐ人は多いものです。しかし、焦って手続きを進めることで、後から取り返しのつかないトラブルや損につながるケースもあるため要注意です。
「早く売りたい」と思って焦って契約→無効になる危険
親が介護施設に入ることが決まり、まとまった資金がすぐに必要になると、「とにかく早く売却しよう」と焦ってしまうことがあります。しかし、売却に当たって最も大切なのは、契約の時点で本人(認知症の親)に意思能力があるかどうかです。
意思能力がない状態で契約を結ぶと、契約自体が無効とされるリスクがあり、最悪の場合は、取引後にトラブルとなって損害賠償を求められる可能性もあります。
特に、家族だけで「意思はある」と判断して進めるのは非常に危険です。意思能力の有無については、不動産会社や司法書士、必要に応じて医師の診断など、第三者の専門的な判断を要します。急いでいる場合でも、まずは法的な要件を満たしているかどうか、丁寧に確認することが大切です。
兄弟の合意なしに話を進めてトラブルに
実家の売却に関わる兄弟姉妹が複数いる場合は、一部の家族が独断で話を進めてしまうと、後から大きなトラブルに発展することがあります。
たとえ不動産の名義が親単独だったとしても、将来的な相続を意識する兄弟がいると「勝手に処分された」と思われることもあり、関係が悪化したり法的な争いに発展したりする可能性も否定できません。
特に注意を要するのは、認知症の親の判断能力が低下している状態で、家族の誰かが売却を主導した場合です。「本当に親が納得していたのか?」「財産の使い道は正当か?」といった疑念を招き、後で相続争いの火種となることも少なくありません。
売却を円滑に進めるためには、事前に兄弟全員で話し合いの場を持ち、方向性について合意しておくことが重要です。
無理な手段を選ぶと後から大きな損失に
委任状を使って代理で売却したり、判断能力があいまいな状態の親に無理やり署名させたりといった「強引な手段」は、たとえ善意であっても重大なリスクを伴います。後になってその手段が不適切だったと判断されれば、契約の無効や損害賠償請求に発展する可能性も否定できません。
また、家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を売却すると、「後見人の義務違反」とみなされて売却益の返還を求められることもあります。こうなると家族間で責任を問われる事態にもなりかねません。
大切なのは、「すぐに売る」ことではなく「後悔しない形で売る」ことです。法的なプロセスや親族の意思を確認しながら、無理のない売却を目指すようにしましょう。
実際のスケジュール感と注意点

「認知症の親の家を売りたい」と考えたとき、気になるのが「実際にどのくらいの期間がかかるのか」「今やるべき準備は何か」という点です。成年後見制度を活用する場合は、通常の不動産売却と比べて時間がかかるため、早めの準備と手続きの把握が重要になります。
また、実家が空き家になっている場合は、固定資産税が上がるタイミングや維持コストについても要注意です。
成年後見制度を使った売却はどれくらい時間がかかる?
成年後見制度を利用して不動産を売却する場合は、最低でも3〜6か月程度の時間を見込んでおく必要があります。売却の手順は以下の通りです。
- 申し立て準備(約2〜3週間):診断書の取得や申立書類の準備など。
- 家庭裁判所への申し立て(審理:約1〜2か月):後見人が適任か、本人の判断能力はどうかなどを審査。
- 後見人の選任と登記(数週間から1か月)
- 不動産の査定・媒介契約・家庭裁判所の売却許可申請(1〜2か月)
- 買い主との契約・決済・引き渡し(通常の不動産取引と同様)
なお、裁判所への申し立てから実際の売却完了までの間に不動産市場の状況が変化することもあるため、「早く売りたい」という人は特に、早めに行動することが重要です。
空き家・実家の固定資産税のタイミングにも注意
認知症の親の家が空き家になっている場合は、固定資産税が変わるタイミングも把握しておく必要があります。
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に課税されます。例えば、3月に売却が成立した場合も、その年の支払者は前所有者(親)です。
また、老朽化した空き家が長期間放置されていると、「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が解除される可能性もあります。優遇措置が解除されると固定資産税がそれまでの6倍になるため、空き家を処分する場合は、とにかく早めに動くことが重要です。
売却前にやっておくべき準備チェックリスト
不動産売却をスムーズに進めるためには、法的手続きだけでなく事前準備も非常に重要です。売却前に確認・準備しておくべきポイントを解説します。
登記簿の確認(名義は親本人か?)
不動産を売却するためには名義の確認が必要です。登記簿謄本で不動産の名義人を確認しましょう。
相続登記は済んでいるか?
不動産の名義が被相続人(故人)名義のままでは売却できません。過去の登記漏れがないかも確認しておきましょう。
売却の理由・方針を家族内で共有
兄弟姉妹間の認識を統一することで、トラブルを未然に防げます。
建物・土地の状態をチェック
建物に老朽化している箇所や過去の修繕履歴があるかどうか、事前に確認しておきましょう。
査定・相場を事前に調べておく
複数の不動産会社から査定を取って売却価格の目安を掴んでおきましょう。
成年後見制度や家族信託などの選択肢を検討
親の判断能力や家族の希望に応じて、制度の利用を視野に入れます。
福岡で相談するなら?地元密着型の不動産会社を選ぶメリット
不動産を売却する際には、関係する家族の気持ちだけでなく、地域の事情を汲み取った対応も求められます。特に遠方に住んでいる場合は現地のことがわからず、相談先をどこにすべきか迷うことも多いでしょう。
そんなときこそ頼りになるのが、地元に拠点を置いて地域に根ざした活動をしている不動産会社です。全国展開の大手にはない、地元密着型ならではの強みや、相談できる公的窓口などについてご紹介します。
地域に根ざした業者が強い理由
地元密着型の不動産会社には以下のような明確なメリットがあります。
地域の相場や事情に精通している
福岡市、北九州市、久留米市など、同じ福岡県内でもエリアごとに不動産のニーズや価格帯は大きく異なります。地元の不動産会社であれば、エリアの特性を正確に把握しており、適正価格での査定や、地元買い主へのスムーズな売却提案が可能です。
柔軟かつ親身な対応を期待できる
認知症の親が所有する不動産を売却する場合は、通常の不動産売却とは異なる配慮を要することが少なくありません。例えば、成年後見制度に詳しい司法書士との連携、相続対策のアドバイス、親族との調整などです。
地元の業者であれば、顔が見える関係の中で、一人ひとりの状況に寄り添った対応を期待できます。
行政・医療・福祉機関との連携力がある
地域に根ざした不動産会社であれば、行政や介護支援の機関とつながりを持っていることも多いものです。介護施設への入所や地域包括支援センターとの連携が必要なケースでも、安心して相談できるでしょう。
福岡独自の空き家対策や制度に対応できる
福岡県や市町村が実施している空き家バンクや税制優遇制度、売却時の補助制度など、地元特有の制度を熟知しているのも地元密着型業者ならではの強みです。売却時に利用できる制度を見落とさず、損のない売却を実現できます。
福岡で相談できる窓口・支援機関一覧
不動産の売却に加え、成年後見制度や家族信託、介護・相続などに関しても、福岡県内にはさまざまな相談窓口があります。状況に応じて、以下のような機関に相談するのも有効です。
| 相談窓口 | 主な相談内容 |
| 福岡県 高齢者地域支援課 | 成年後見制度・空き家対策・福祉制度全般 |
| 地域包括支援センター | 認知症支援・生活支援・介護サービスの紹介 |
| 弁護士会の法律相談センター | 成年後見申し立て・委任状作成・相続問題 |
| 福岡県 司法書士会 | 後見制度・信託契約・登記関係の相談 |
| 福岡県 宅地建物取引業協会 | 売却のトラブル・媒介契約の内容など |
上記の相談窓口は予約制となっている場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
よくある質問Q&A
認知症と不動産売却の問題は複雑で、状況によって判断が分かれることも多くあります。ここからは、相談の中でも特に多い3つの質問についてお答えします。
Q:親が話せるうちに売った方がいいの?
A:はい。売却を考えているなら、親の意思確認ができるうちに手続きを進めるのが理想です。
親に意思能力があれば、本人の同意のもとに通常の売買を進められます。逆に認知症の症状が進んでからでは、成年後見制度などの法的手続きが必要になり、時間も費用もかかります。
Q:後見人は家族でもなれる?
A:はい。家庭裁判所が認めれば、子どもや配偶者などの親族も後見人になれます。
なお、申し立ての際に希望を伝えることは可能ですが、最終的な決定を下すのは家庭裁判所です。被後見人(親)の利益が最優先されるため、財産管理や親族間トラブルの有無などが判断材料になることが多くなっています。
Q:委任状があるけど、それで売って大丈夫?
A:委任状だけでは不十分な場合があります。本人に意思能力がない状態で作成された委任状は無効とされる可能性が高いため要注意です。
不動産売買は重要な法律行為であり、委任状を有効とするためには「本人が内容を理解し、意思をもって署名すること」が必要です。判断能力が低下した後に委任状を作成すると、売却後に契約無効を主張されるリスクもあります。
認知症の親の不動産売買ならグラングッド不動産へ
認知症の親の不動産を売却するためには、法的な手続きや家族間の調整、福祉的な配慮など、通常の不動産取引とは違った複雑さに対応する必要があります。そんなとき、信頼できる相談先があると大きな安心につながるでしょう。
福岡県で不動産の売却や相続、住み替えの相談を検討されている方には、地元密着型のグラングッド不動産がおすすめです。
グラングッド不動産では、単なる売却のサポートにとどまらず、老人ホームの紹介や相続・贈与への対応、不動産の管理やリフォームといった人生設計全体に寄り添うサービスを展開しています。
また、法的な手続きが必要なケースにおいても、提携する専門家と連携し、後見制度や家族信託の活用を見据えたスムーズな売却支援が可能です。
売却後の税金・資金計画や万が一のトラブルへの備えも、丁寧にサポートします。将来の住まい探しや資産活用の場面でも、「売ったら終わり」ではなく一生涯の相談パートナーとして対応します。
福岡エリアで「誰に相談したらいいかわからない」とお悩みの方は、まずは一度グラングッド不動産にご相談ください。ご家族にとって最適な選択肢を見つけるお手伝いをさせていただきます。
まとめ
認知症の親の不動産をスムーズに売却するためには、本人の意思能力の有無を慎重に判断し、必要に応じて成年後見制度や家族信託などの法的手段を活用することが必要です。
焦って手続きを進めると契約の無効や家族間トラブルにつながるリスクもあるため、冷静な対応と事前準備が欠かせません。信頼できる相談先が見つかれば、複雑な手続きもスムーズに進められます。地域の事情に詳しい不動産会社や専門家を頼りながら、安心・安全な方法で資産整理を進めましょう。